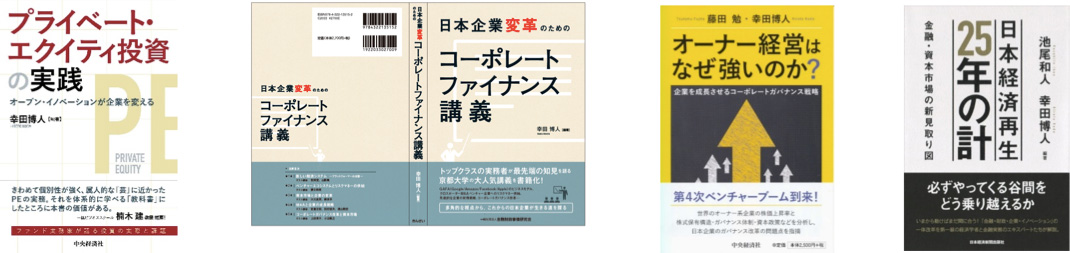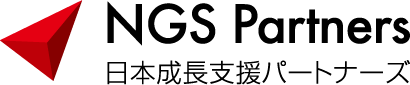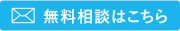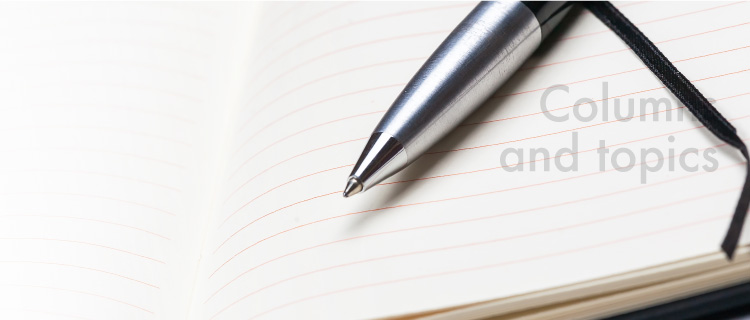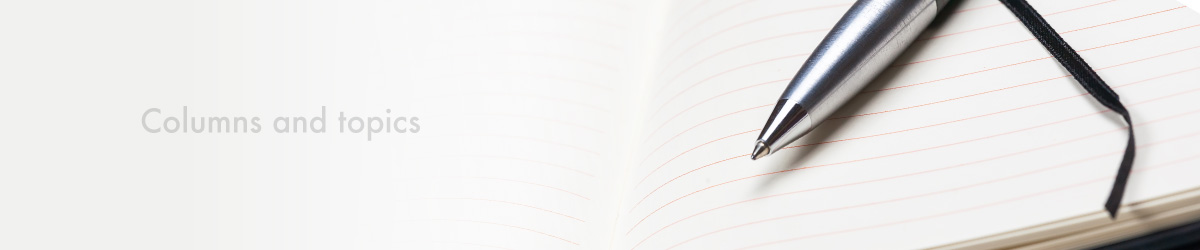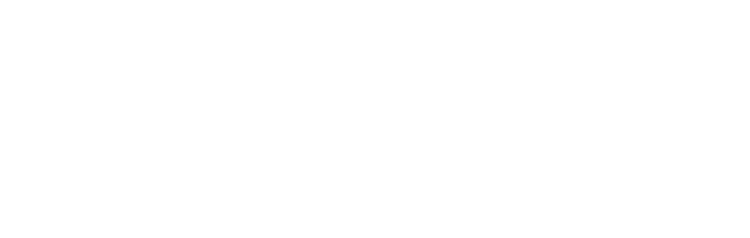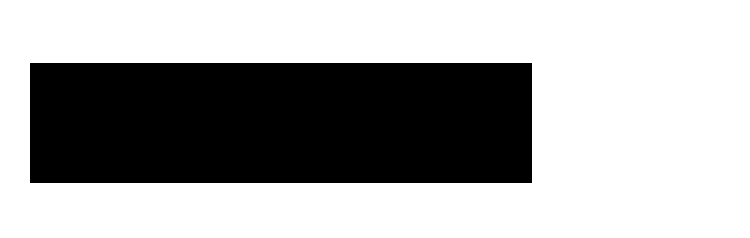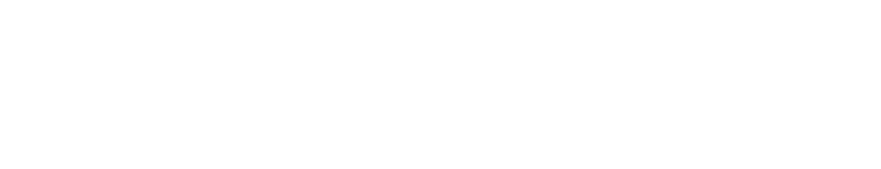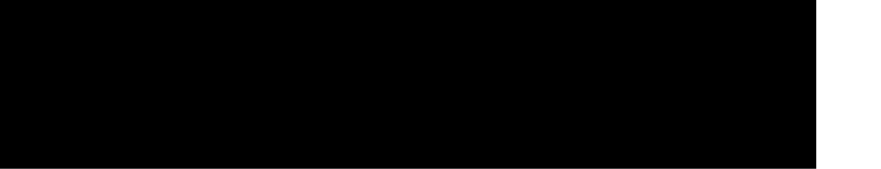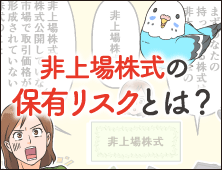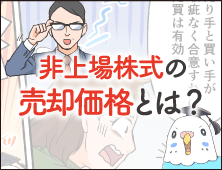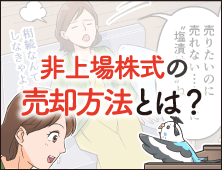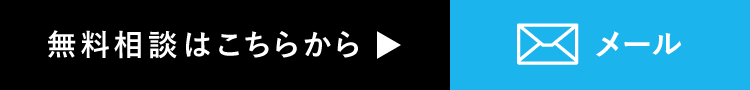親や親族が会社を経営していて、非上場株式(未上場株式、未公開株式ともいう)を持っている場合、相続時にどれくらいの相続税がかかるのか気になりませんか?
実は、非上場株式の評価はとても複雑で、思っている以上に高額な相続税が発生するケースもあるんです。
「そもそも非上場株式ってどうやって評価されるの?」
「会社を引き継ぐ気がないのに、多額の相続税を払わないといけないの?」
こうした疑問を抱く方は非常に多く、事前に対策しているかどうかで、将来の税負担に大きな差が出ることも。
この記事では、非上場株式の相続に関する基礎知識と、よくある落とし穴・対策方法をわかりやすく解説します。
目次
1. 非上場株式とは?上場株式との違い
「非上場株式」とは、証券取引所に上場していない会社の株式のことを指します。多くの場合、家族経営や中小企業のオーナーが保有しており、市場で自由に売買することはできません。これに対して、上場株式は誰でも市場で簡単に売買でき、時価(株価)が明確に存在します。
非上場株式は売却が難しい一方で、相続の際には「資産」として評価され、相続税の対象になります。その評価方法が複雑で、想像以上の金額になるケースも珍しくありません。
2. 非上場株式にかかる相続税の仕組み - 相続税評価額とは
相続税を計算する際は、まず財産ごとの相続税評価額を求める必要があります。相続税評価額とは、相続や贈与で引き継がれる財産の価値を、税務上のルールに従って金額化したもので、この相続税評価額を基に相続税が計算されます。現金・不動産・株式など種類によって評価方法が異なり、特に非上場株式は市場価格がないため、国税庁が定めた以下の3つの評価方式を使って計算されます。
① 類似業種比準方式:業績が良いと評価額が高くなる
この方式は、上場している同業他社の株価や業績を参考にして、相続する会社の評価額を算出する方法です。具体的には、売上・利益・配当などの指標を基に比較されます。
- 特徴:
- ●業績が良い会社ほど評価が高くなる
- ●同業の上場企業と比較されるため、利益率の高い企業には高評価になりやすい
- ●配当を出していると評価額がさらに上がる傾向
② 純資産価額方式:会社が持つ資産ベースで評価
この方式は、会社が保有する資産や負債を基にして、「解散したときに残る価値」で株価を評価します。帳簿上の資産額を修正し、時価に近づけて算出するのが特徴です。
- 特徴:
- ●不動産や現預金を多く持つ会社は高評価になりやすい
- ●業績にはあまり影響されない
- ●資産家型の会社には評価が高くなりやすい
③ 配当還元方式:配当だけで評価するシンプルな方法
この方式は、過去の配当実績に基づいて評価額を出す、比較的シンプルな方法です。原則として、少数株主向けに使われます。
- 特徴:
- ●配当が少ない(または出していない)会社だと評価が低くなる
- ●簡便な方式で、他の方式に比べて評価額が安くなりやすい
- ●議決権のない少数株主に限定して使われる
どの評価方式を基づき算定されるかは、「株主の判定」「会社規模の判定」により決められます。
3. よくあるトラブル・失敗例
非上場株式を相続したときによく起きるのが、「現金がないのに相続税だけ高くなる」という問題です。
特に非上場の少数株式は、
- ●取引市場がない
- ●買い手が少ない
- ●譲渡時に会社の承認が必要(譲渡制限株式)
- ●価格が不透明
などの理由から非常に売りにくい(流動性が低い)というのが現実です。
株式を売れなくて(現金化できなくて)、税金を払うために銀行借入を行い、納税資金を準備したというケースもあります。
そのため、相続などで非上場株式を取得する場合、または取得することが見込まれる場合には、「簡単に現金化できない資産」であることを理解し、早めに対策を考えることが重要です。準備不足や知識不足が、想定外の損失や家族間の争いにつながる可能性があります。
4. 専門家に相談すべきタイミングと理由
非上場株式の評価や株式売却などの相続税対策は、税理士や専門家のサポートが不可欠です。評価方法は複雑で、また買い手探しから売却に至る手続きも独力で適切に対応するのは非常に困難です。
特に非上場の少数株式の株主が以下のようなケースに直面している場合は、専門家に相談すべきタイミングかもしれません:
- ●株式の評価額が高く、相続税も高額になる見込みなため、相続が発生する前に速やかに現金化したい
- ●発行会社が買い取りに応じてくれない
- ●発行会社から提示された買取価格が安価である
- ●発行会社以外の買い手候補がいなくて、発行会社に足もとをみられた交渉をされる
- ●妥当な株価が分からない
まとめ:早めの準備が、トラブルと損失を防ぐカギ
非上場株式の相続は、「評価額が高くなる」「現金化できない」「トラブルになりやすい」という三重苦があります。
しかし、知識を持って早めに対策することで、相続税の負担も、家族の争いリスクも、大きく減らすことができます。
まずは、現状の株式評価や会社の財務状況を把握し、信頼できる専門家に相談してみることが、トラブルを未然に防ぐ最初の一歩です。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)