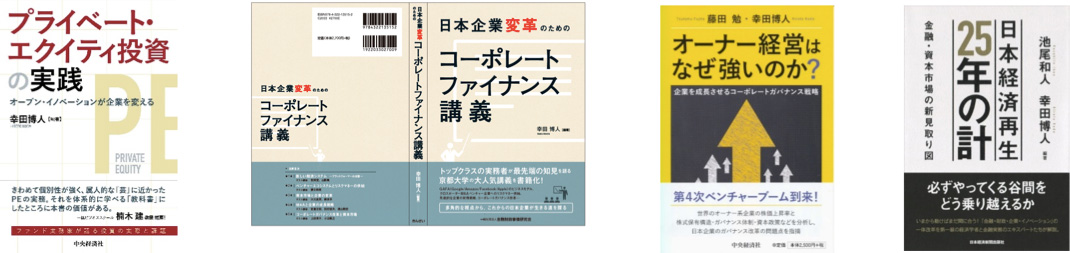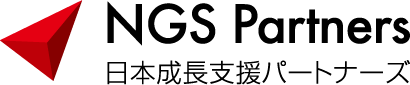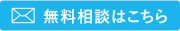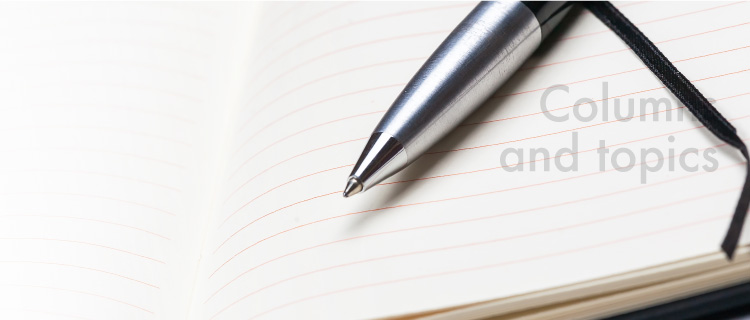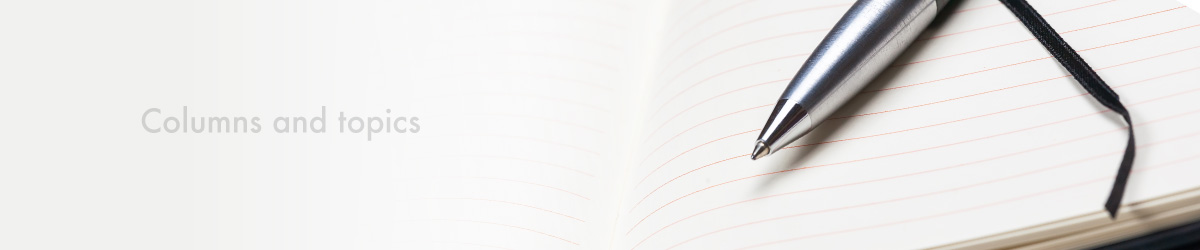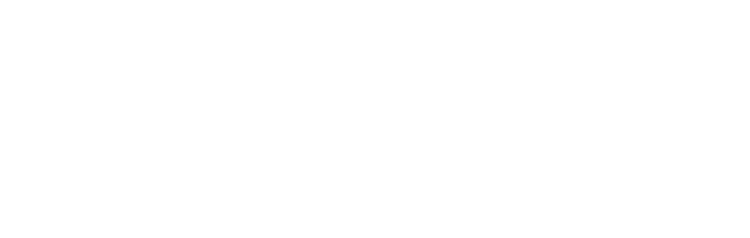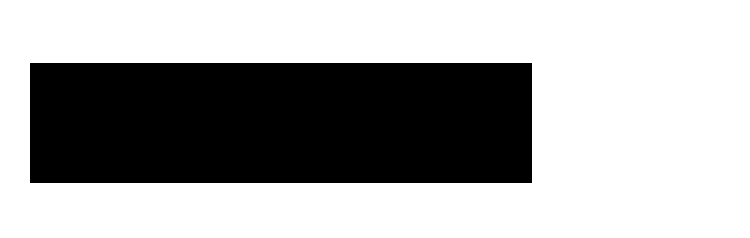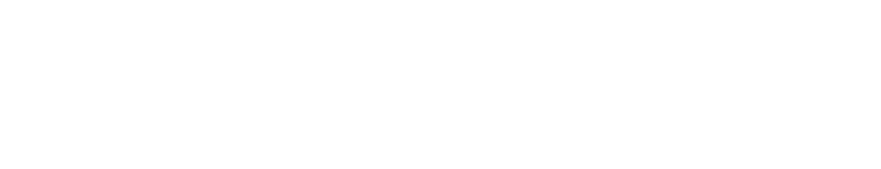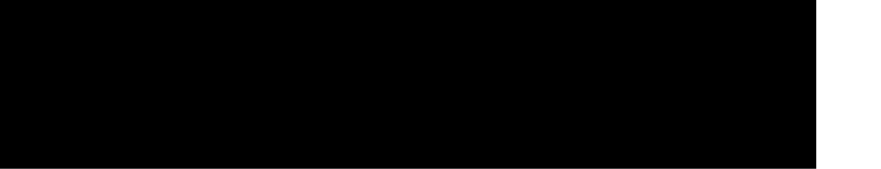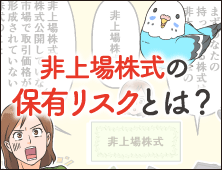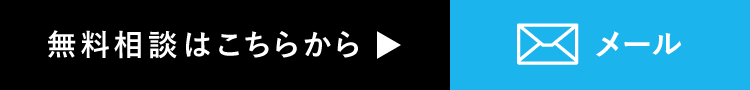目次
1. はじめに:配当は安心材料か?それとも現実逃避か?
あなたが保有している未上場企業(非公開会社)の株式から、毎年一定額の配当が支払われているとします。
「毎年もらえているし、売却しなくてもいいのでは?」
そう感じている少数株主は少なくありません。
しかし、本当にそうでしょうか?
配当が出ていることと、その会社が健全経営をしているかどうかは必ずしも一致しません。
ましてや、将来その株式を希望通りに売却できるかどうかは、まったく別の問題です。
今回は、未上場・同族企業の少数株主の方に向けて、配当と成長、そして「株式の出口戦略」について考えるヒントをお届けします。
2. 未上場企業の配当──なぜ出し続けるのか?
配当金が毎年出ている会社の中には、実は赤字決算にもかかわらず定額配当を維持しているケースがあります。
特に同族会社(ファミリービジネス)では、その傾向が顕著です。
その背景には、以下のような理由が挙げられます。
- ・オーナー自身の資金需要:役員報酬とは別に、生活費や納税資金を確保したい
- ・少数株主への配慮:配当がなければ何のリターンも得られない非上場株主への“誠意”
- ・慣習の踏襲:先代から「毎年出すのが当然」という空気が続いている対外的アピール:金融機関や取引先に“経営の安定性”を印象づけるための配当
こうした配当は、確かに受け取る側にとっては安心材料になります。
しかしその裏で、本来、将来のために回すべき資金が社外に流出している可能性もあるのです。
3. 成長企業なら、本来は「投資優先」が基本
資金に限りのある未上場企業が、将来の成長を目指すなら、利益は内部留保または事業投資に回すべきです。
にもかかわらず、惰性的に配当を継続していると、以下のような機会が失われる可能性があります:
- ・設備投資、新規事業開発、DX推進
- ・優秀な人材の採用・教育
- ・営業活動の強化・ブランド構築
本来、こうした分野にこそ、利益を再投入するべきです。
にもかかわらず、赤字でも配当を出すような未上場の同族企業では、経営の意思決定が「将来の成長」よりも「慣習と顔色」を優先している恐れがあります。
4. オーナー経営の配当方針──“誠意”か“経営の甘え”か
同族経営にありがちな現象として、「過去の方針を変えないことが誠意」とされる空気があります。
たとえば、三代目や四代目の後継者が、「祖父の代から出してきたから」という理由で、赤字決算でも定額配当を出し続けていることがあります。
これは一見、株主への誠意のように見えますが、実態としては経営の惰性・思考停止である可能性があります。
少数株主にとっては嬉しい話かもしれませんが、企業価値が長期的に毀損すれば、最終的には株の売却価値にも悪影響を及ぼします。
5. 少数株主として、将来の売却に向けて今できること
将来的な株式売却を見据える少数株主は、表面的な配当だけで安心せず、次の行動を静かに準備すべきです。
- ●株式を持つ会社の実態を把握しておく
- ・配当の原資が利益なのか、過去の蓄積の取り崩しなのか
- ・財務状況、借入残高、売上推移、業界動向などを見ておく
- ●株式の出口戦略を考えておく
- ・誰に・どうやって売れるのか? オーナー?会社?第三者?
- ・会社法上の制限(譲渡承認など)や定款を確認する
- ●他の株主と連携できる関係を築いておく
- ・同族株主以外がいる場合は、情報共有できる信頼関係を保っておく
- ●外部の専門家に早めに相談
- ・M&A支援業者や、非上場株式の売却に強い弁護士・税理士と連携
- ・相場観・交渉の戦略・相続時の対応などを見据えた相談が有効
6. 〈実話に学ぶ〉配当に安心していた少数株主の“後悔”
以前、弊社にご相談いただいた案件の中に、こんなケースがありました。
ある地方の同族企業で、古くから経営に関わっていた元役員の方が、退任時に自社株を譲り受け、そのまま20年以上保有されていました。
会社は毎年安定的に配当を出しており、「持っていればお金が入ってくるし、特に困っていない」と、特段のアクションも起こさずにいたそうです。
ところが、業績の悪化を受けて配当が突如停止。さらに、創業家のオーナーが急逝し、後継者とは接点がなく、株式の扱いについて相談すらできない状態に。自身の相続のことも心配になり、いざ売却を検討しても、会社からは「買い取る予定はない」と言われ、買い手も見つからず、「配当もない、売ることもできない」という行き詰まりに直面されていました。
このケースが示すのは、「配当が出ているから安心」という思い込みのリスクです。非上場株式は、売却できる道筋を事前に描いておかない限り、資産価値があっても“出口のない資産”になり得ます。
7. おわりに:株式の“出口”を見据える株主こそ、経営の鏡である
配当が継続している未上場企業を保有していると、つい「安定している」「このまま持っていればいい」と考えてしまいがちです。
しかし、現金をもらい続けながら、株式そのものの価値は目減りしているかもしれないことを忘れてはいけません。
“出口戦略”を意識した株主こそ、経営に緊張感を与える存在です。
配当に甘えるだけでなく、冷静に、静かに、着実に。
あなたの持株が、将来「売れる資産」として残るよう、今から備えておきましょう。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)