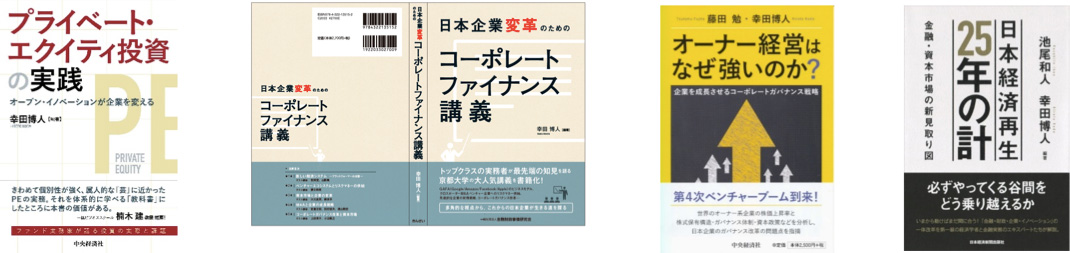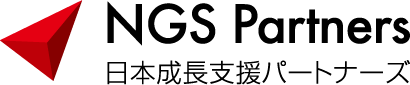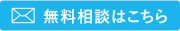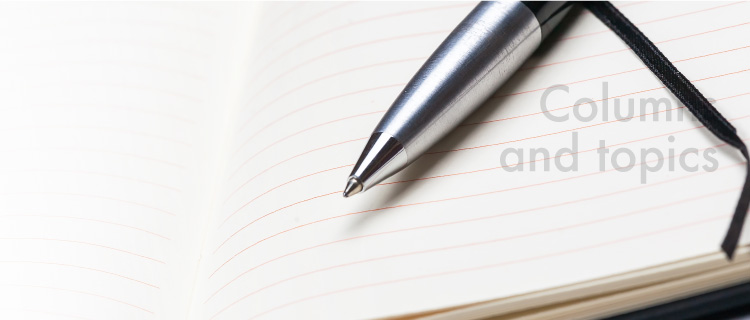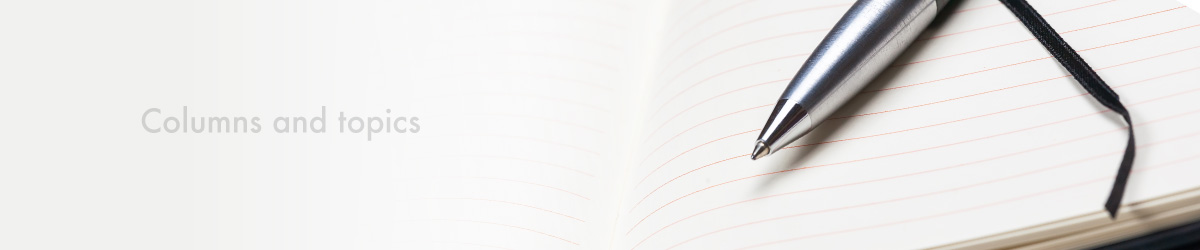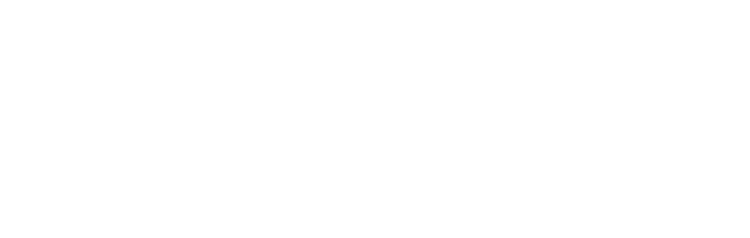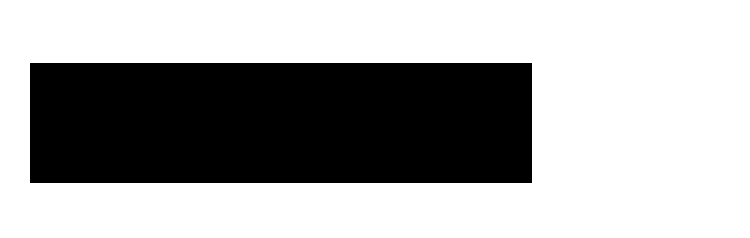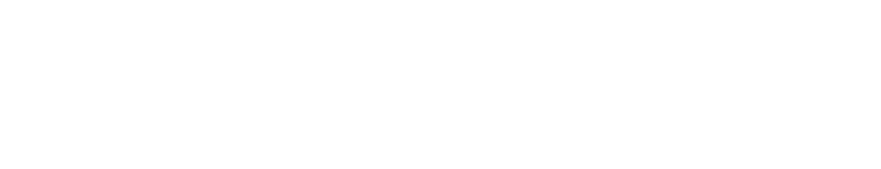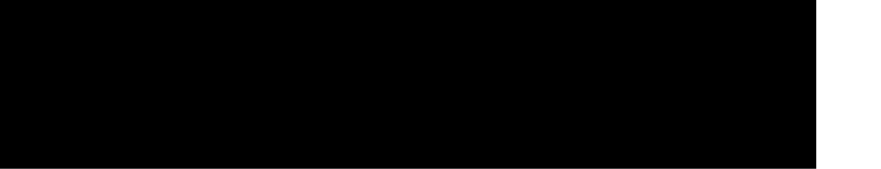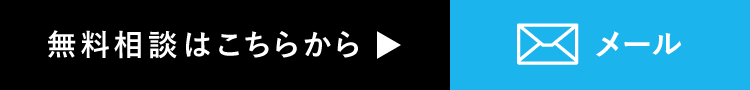はじめに
非上場企業において、株式分散は時間の経過とともに静かに進行する“構造的なリスク”です。特に創業からの歴史が長い企業ほどその傾向は強く、さらに個人株主が多い場合には、相続を繰り返す中で株主数が加速度的に増えていきます。
この株式分散は、放置すれば経営や株主関係に深刻な影響を及ぼす可能性があります。本コラムでは、株式分散の背景やリスクを整理し、企業タイプ別に大まかな対応の方向性をご紹介します。
1. 株式分散が進む背景
株式分散は、次のような要因が積み重なって進行します。
- ・世代交代による相続
株主が亡くなるたびに、株式は複数の相続人に分割されます。 - ・個人株主の相続連鎖
個人株主が多い場合、それぞれの株式がさらに相続を繰り返し、株主数が雪だるま式に増加します。 - ・過去の資金調達や従業員持株会
退職者株式がそのまま残るケースや、関係者への譲渡株が長期間外部に留まるケースも少なくありません。
このような株式分散は、一度進むと元に戻すことが難しく、早い段階での対応が求められます。
2. 株式分散による代表的なリスク
株式が広く分散すると、企業は次のような課題に直面します。
- 1.意思決定の停滞
株主総会で特別決議が通りにくくなり、重要な経営判断が遅れる。 - 2.株式の流動性低下
株主が売却を望んでも、買い手が見つからない/価格が不透明になる。 - 3.株主間や経営陣との関係悪化
情報格差や意見の食い違いから不信感が生じる。 - 4.事業承継や資本政策の難航
後継者への株式集約が困難になり、M&Aの選択肢も狭まる。
3. 対策の基本的な考え方
株式分散への対応で大切なのは、売却を希望する目の前の株主への対応という目先の取引だけを考えるのではなく、将来どういう株主構成にしたいのかという長期的なビジョンを描くことです。
そのビジョンを起点に、株式の流れや相続の発生を見据えて計画的に対策を講じることで、経営の安定と企業価値向上につなげることができます。
4. 企業タイプ別の方向性
① オーナー系企業
- 特徴:オーナーまたは特定株主が経営の中心を担い、意思決定の一貫性が求められる。
- 方向性:明確な目的は「オーナーまたは特定株主への株式集約」。
資金調達の方法や取得のスケジュールを計画的に検討することで、着実な株主構成の再構築が可能になります。
② 大手企業の子会社
- 特徴:親会社が過半数を保有し、残りを法人株主や多数の個人株主が持つ構造。経営陣は親会社からの出向者で定期的に交代し、自分の在任中に少数株主の整理といった手間のかかることを、あえて進めたいと考える人は少ない。さらに、親会社も規模が大きなグループになればなるほど、数ある子会社の一社に過ぎない当該会社の株主政策は子会社任せとなる傾向が強く、親会社の中で株主政策を検討する優先順位は低い。結果として、そもそも株主政策に着手するインセンティブが働きづらい構造にある。
- 課題:
- 1. 株式集約の主体や資金の出どころが曖昧になりやすい。
- 2. 自社株買いを行う場合、
- ・特定の株主から買い取るには特別決議が必要で、同時に潜在的な売却希望者が一気に表面化するリスクがある。
- ・多額の買取資金をどう確保するかという財務面の負担が大きい。
- 方向性:まずは親会社の株主政策の方針を明確化し、将来の株主構成に関する合意形成を図ることが第一歩となります。
5. おわりに
株式分散は、静かに、しかし確実に進行する課題です。
重要なのは、問題が顕在化してから慌てて対応するのではなく、「将来のあるべき株主構成」から逆算して早期に手を打つことです。企業タイプによって有効な手段やアプローチは異なりますが、いずれの場合も長期的な視点での株主政策が、経営の安定と企業価値向上の基盤となります。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)