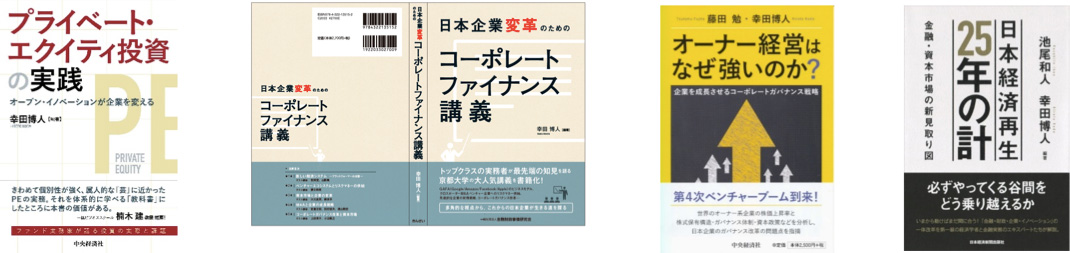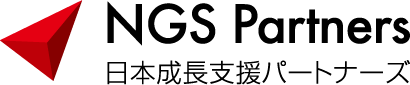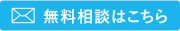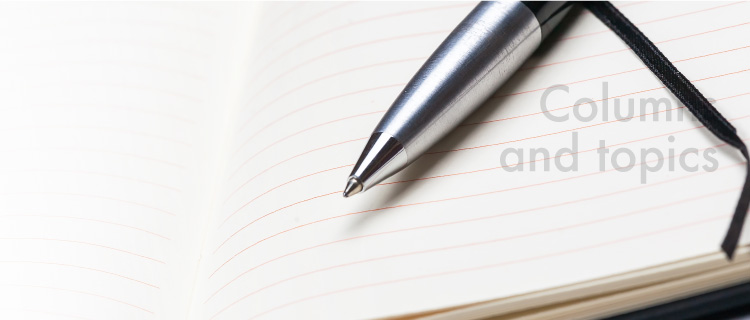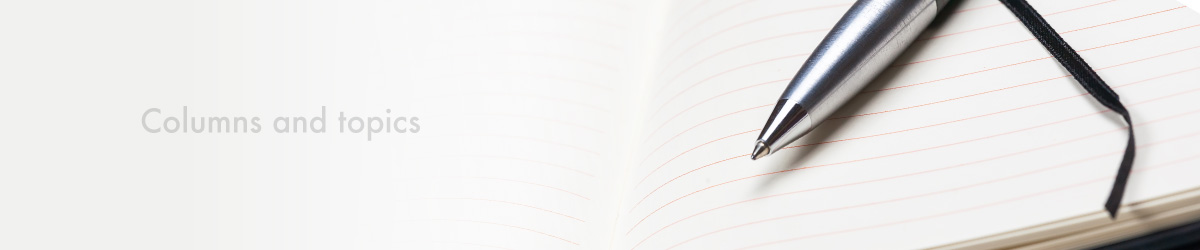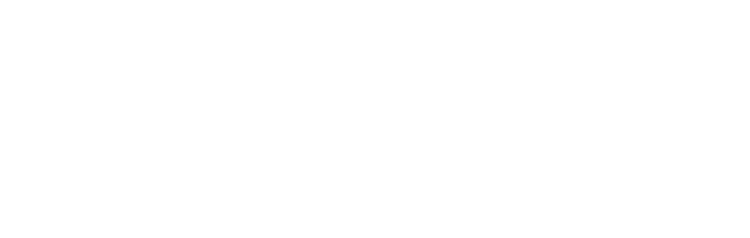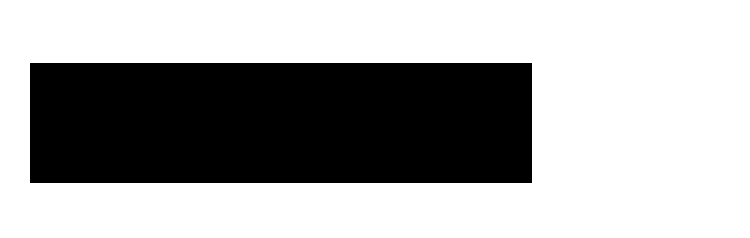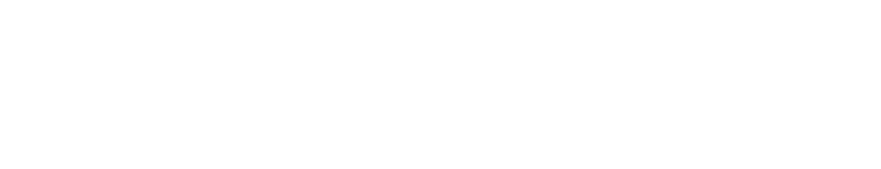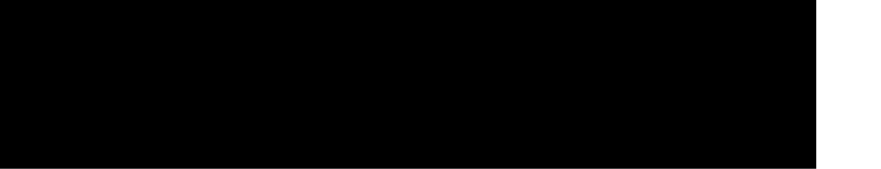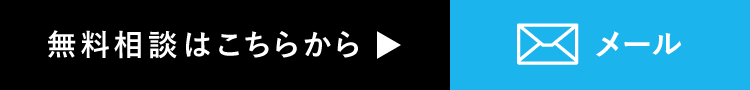はじめに
上場企業ではコーポレートガバナンスの要として社外取締役制度が定着していますが、非上場企業においても社外取締役の重要性は高まっています。特に株主構成が複雑化し、少数株主や外部株主の声が経営に届きにくい企業では、社外取締役が果たす「株主・利害関係者の代表」という役割が経営の健全性を保つ鍵となります。
1. 非上場企業特有の株主構造と課題
非上場企業では、創業家、役員、従業員持株会、相続によって株式を取得した親族や第三者など、多様な株主が存在します。特に創業からの歴史が長い企業ほど、株式の分散傾向が強くなります。
その背景には、次のような要因があります。
- ・世代交代による相続
創業者や大株主の相続のたびに、株式が複数の相続人に分割されます。 - ・個人株主が多い場合の加速度的な分散
個人株主が多いと、それぞれの株式がさらに相続を繰り返し、株主数は雪だるま式に増加します。 - ・退職者や関係者の保有株式
従業員持株会や過去の関係者への株式譲渡が、その後も社外に残り続けるケースもあります。
こうした企業では、株主間の情報格差や発言機会の少なさから、経営判断が一部株主の都合に偏ってしまうことがあります。とりわけ少数株主にとっては、株式の売却や資産運用の自由度が低く、「株主としての声」が経営陣に届かないまま時間だけが経過するケースが少なくありません。
2. 実際にあった相談事例
非上場企業では、①資金調達の制約と②非上場株式の流動性の低さによる買い手不足という二つの要因から、株式の売却希望に柔軟に対応することが難しいケースが少なくありません。
実際、ある企業からは次のような相談が寄せられました。
「複数の個人株主から売却希望が寄せられているが、会社として特定の株主から自社株を買い取るには特別決議が必要でハードルが高い。さらに、潜在的な売却希望者が一気に表面化し、買取資金の確保という財務面での負担が急増する懸念もある。持株会の活用や、自社の取引先を紹介して相対取引で対応する方法にも限界がある。何か打開策はないだろうか。」
この企業では、少数株主が株式を売却したくても売り先が見つからず、会社としても自社株買いに必要な資金を十分に確保できないという課題を抱えていました。結果として、売却希望が寄せられても対応策は場当たり的になり、抜本的な解決には至っていなかったのです。
3. 社外取締役が果たす「株主・利害関係者の代表」機能
こうした場面で、社外取締役は重要な役割を担います。
- ・中立的な立場で少数株主や外部株主の意見を拾い上げる
- ・株主と経営の間の“橋渡し役”となり、意見を取締役会で代弁する
- ・株主構成の安定化や企業価値向上につながる施策を提案する
特に、資金面の制約や株式の流動性の低さが課題となる場合には、社外取締役が外部ネットワークや第三者の知見を活用し、売却先の可能性を広げるといった実務的な貢献も可能です。さらに、経営陣に対しては「株主構成の安定化策」や「長期的な資金計画」の必要性を促し、同様の課題が繰り返されない仕組みづくりを提案できます。
4. 社外取締役導入のメリット
- ・株主間や株主と経営陣との間の信頼関係を強化
- ・対立や不満が深刻化する前に課題を顕在化させ、解決に導く
- ・外部の視点を取り入れ、ガバナンス体制を改善
- ・株主構成の長期的安定と企業価値の向上に寄与
特に非上場企業においては、売却先不足や資金調達の難しさといった構造的な課題が、少数株主の不満や経営陣への不信感に直結しやすくなります。社外取締役が間に入り、客観的な立場で課題を整理し、双方が納得できる解決策を提示できれば、株主間の関係悪化を防ぎ、企業の持続的成長を下支えすることができます。
5. おわりに
非上場企業こそ、株主・利害関係者の声が埋もれやすく、経営判断が一部に偏るリスクがあります。
社外取締役は、その声を経営に届ける“橋渡し役”として機能し、企業の持続的成長を支える存在です。株主の信頼を得ながら企業価値を高めていくために、社外取締役の活用を積極的に検討する価値があります。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)