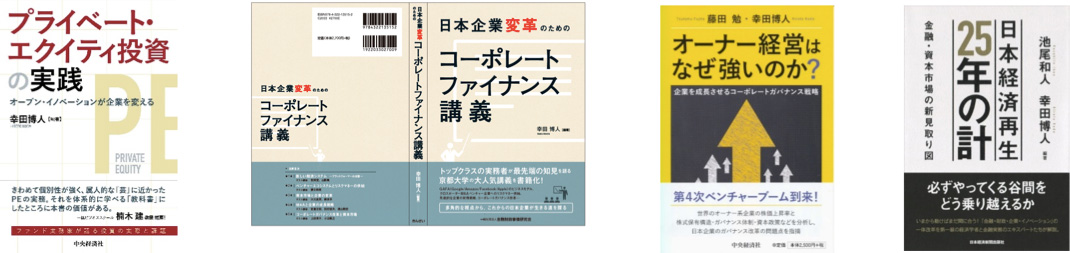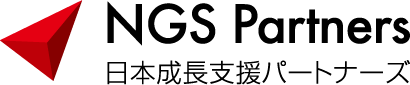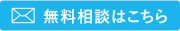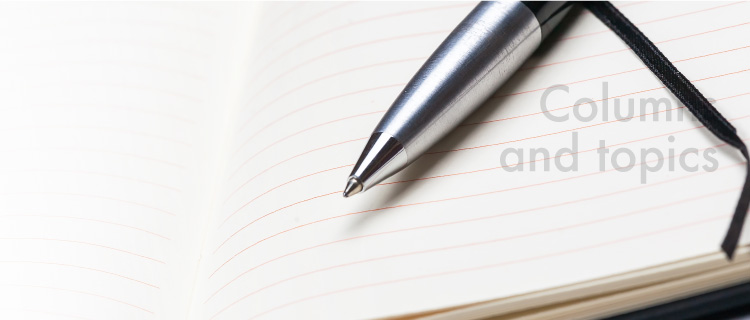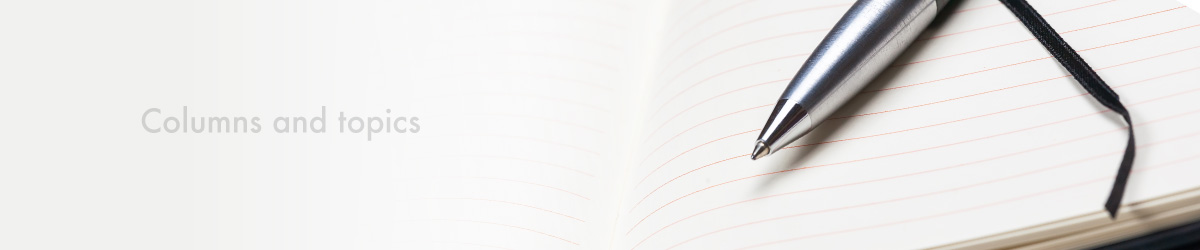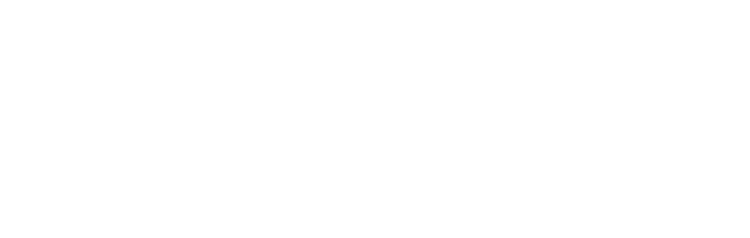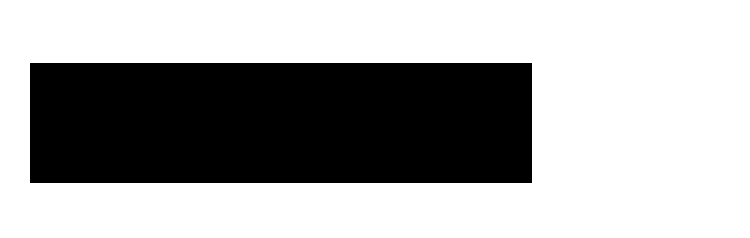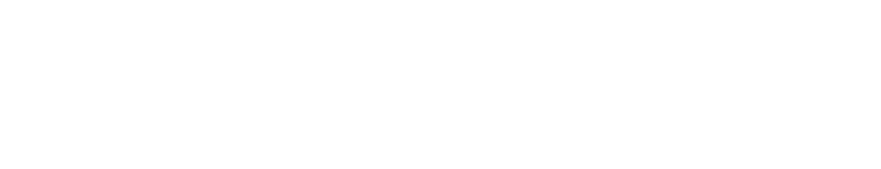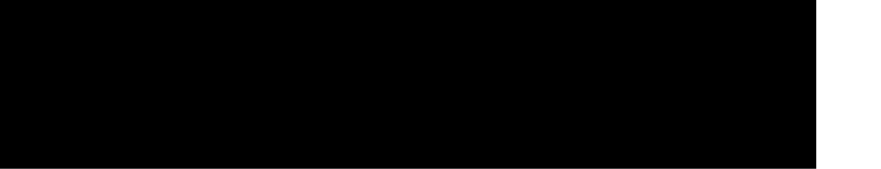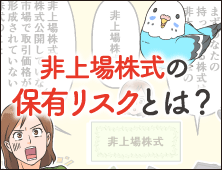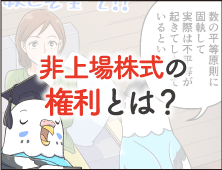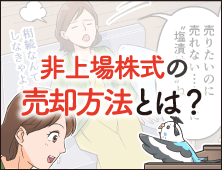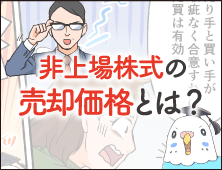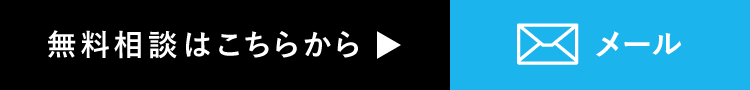未上場企業(同族会社)の株式、特に少数株式を売却したいと考えたとき、思ったように話が進まないことは珍しくありません。会社側が買い取りに応じない、会社から提示された価格が不当に低い、そもそも買い手が見つからない…。こうした中で泣き寝入りを強いられる少数株主も多いのが現実です。未上場株式は取引相場がなく、会社と株主の情報格差も大きいため、交渉力に差が出やすいのです。そこで今回は、未上場株式の売却で「泣き寝入り」しないためのポイントを解説します。
目次
1.「泣き寝入り」になりやすい背景とは
未上場企業、特に同族会社では、株式の流動性が低く、売却希望者が不利な立場に置かれがちです。株価の算定基準が不透明で、情報が会社側に偏る傾向もあります。また、発行会社にとって自社株の買い取りは資金負担が大きく、経営権維持の観点からも、経営に影響力を持たない少数株式の買い取りには、消極的になりがちです。さらに、未上場企業の少数株式の売却に関しては、法律や税務、株価算定、具体的な買い手探しなど複雑な知識が求められる一方で、専門家が少ないという現状があります。こうした構造的な問題が「泣き寝入り」を生みやすい要因となっています。
2.ポイント①「事前に準備する情報と交渉材料」
泣き寝入りを避ける第一歩は、交渉のための材料をしっかりと準備することです。まずは株主名簿や会社の決算書類、招集通知など、会社の内部情報を入手・整理しておきましょう。これらは株式の価値を検討する上で重要な資料となります。また、同族株主間の取引の場合は、自社株の株価算定方法(類似業種比準方式や純資産価額方式など)を理解し、目安となる株価を事前に把握しておくことも不可欠です。こうした準備が交渉時に役立ち、相手側に言いくるめられるリスクを減らすことに役立ちます。専門家に相談し、戦略を練る準備を怠らないことが大切です。
3.ポイント②「適正価格を見極める」
未上場株式は取引相場が存在せず、会社側の一方的な評価や提示額に押し切られがちです。しかし、売却する株式の価値を正確に見極めることが、泣き寝入りを防ぐ鍵となります。同族株主間の取引の場合、株価算定には、類似業種比準方式、純資産価額方式、さらには配当還元方式など複数の方法があります。もちろん、自分で株価算定できるようになる必要は一切ありません。ただ、色々な算定方法があり、自分の株式はどの方法で算定すべきか確認することで、保有する株式がどの程度の価値を持つか把握でき、提示された価格が妥当か否かを冷静に判断できます。もし価格が不当に低いと感じた場合は、その理由を問い、再提示を求める姿勢を持つことが重要です。
4.ポイント③「税務の視点からも適正価格を検討する」
ポイント②にも関係しますが、税務上の観点からも適正価格(いくらで取引すべきか)の把握も重要です。特に同族株主間の取引の場合、税務上の「時価」と大きく乖離した価格で売却すると、「みなし譲渡」や「みなし贈与」など、想定外の税負担が生じる可能性があります。税務上は、時価に基づいた取引を行うことが大切です。
一方で、純然たる第三者との取引であれば、取引価格が税務上の時価として認められるため、税務上の問題は生じにくいことも理解しておきましょう。税務リスクを回避するためにも、専門家の意見を取り入れつつ、慎重に取引価格を決定していくことが大切です。
5.ポイント④「交渉戦略を立てる」
交渉の場では、感情的にならないことが重要です。提示された価格に対し、準備した資料や専門家の意見を根拠に冷静に説明することで、説得力が増します。また、会社側との交渉と並行して、第三者の買い手候補を探すことも大切です。外部の買い手の存在は、会社側にとっても価格見直しや態度変化を促す材料となり得ます。会社のみと交渉するのではなく、買い手の選択肢をたくさん持った上で、自分にベストな売却プロセスを進めようとする姿勢が重要です
6.ポイント⑤「専門家の力を借りる」
少数株式の売却は、法律や税務、株価算定、具体的な買い手探しなど複雑な知識が求められます。経験豊富な弁護士や税理士、少数株式の売却支援を専門的に行うアドバイザーの力を借りることで、より適切な戦略が立てやすくなります。専門家は法律面だけでなく、交渉戦略や株価評価、相手側(会社側、第三者の買い手候補)との調整までをサポートしてくれます。特に未上場株式や同族会社に関する実務経験が豊富な専門家を選ぶことが、成功のカギとなるでしょう。専門家の得意分野を理解した上で、必要に応じて複数の専門家の意見を取り入れ、最善の方針を見極めることが大切です。
7.まとめ
未上場企業の株式売却では、少数株主が「泣き寝入り」するケースが後を絶ちません。しかし、適切な情報収集、冷静な価格判断、戦略的な交渉、そして信頼できる専門家の力を借りることで、より有利な条件を引き出すことは可能です。早めの準備と冷静な対応を心掛け、自らの権利を守るべきです。しっかりと準備をした上で、状況を見極めて一歩ずつ進めることが、泣き寝入りを避ける最善策です。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)