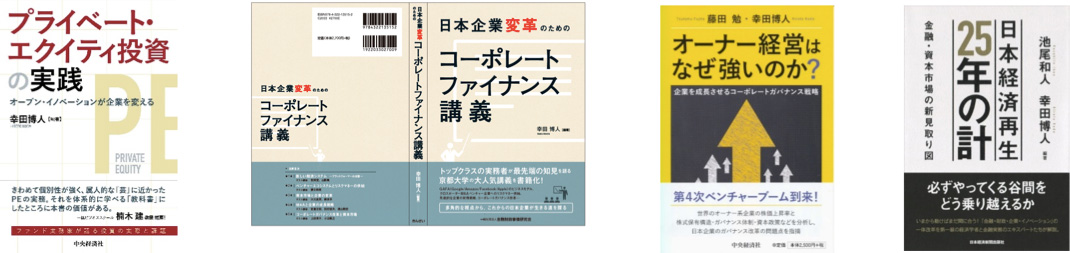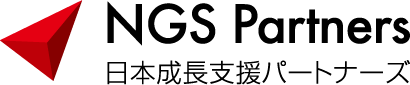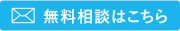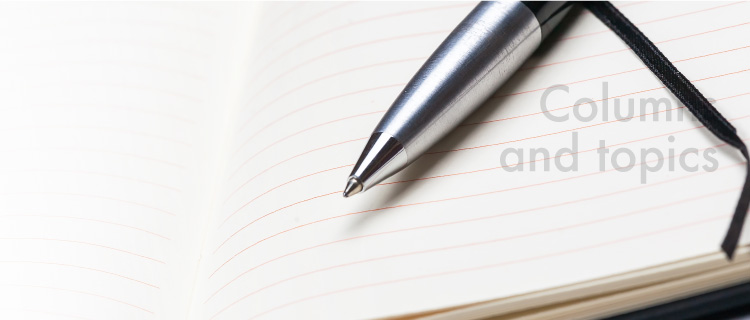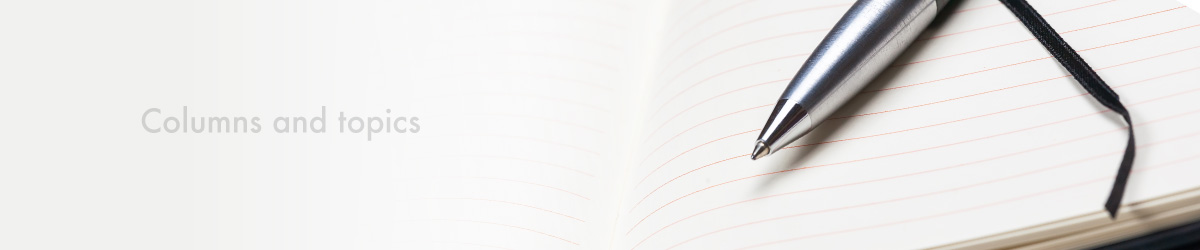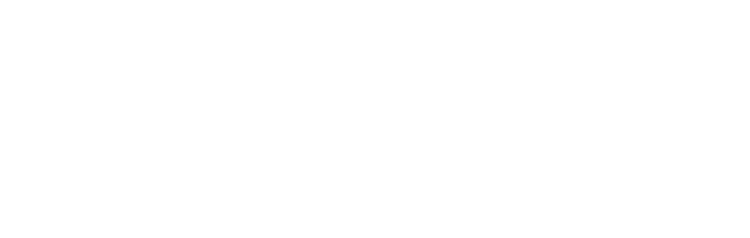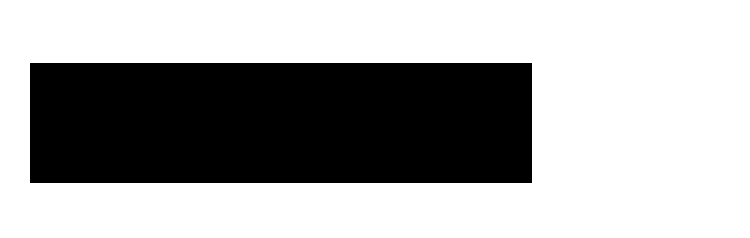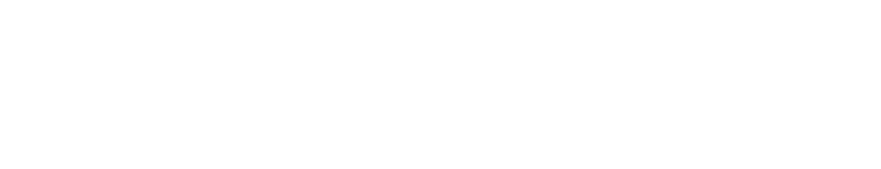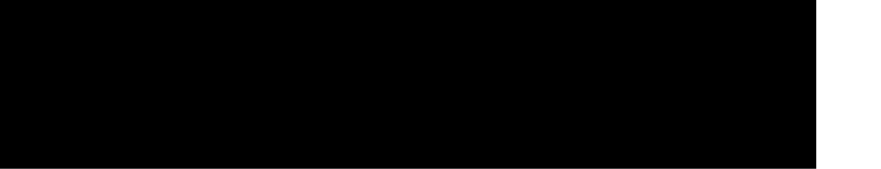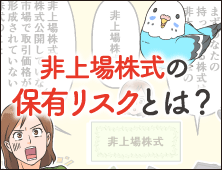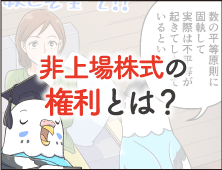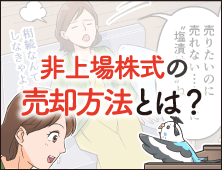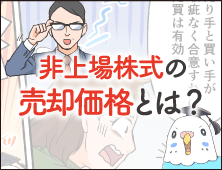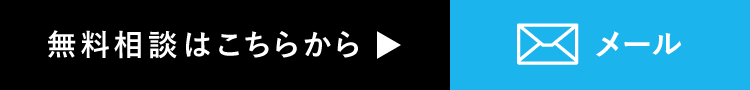親や親族が亡くなり、相続の手続きを行うなかで「非上場株式」が財産に含まれていた場合、相続人にとって頭を悩ませる問題となることがあります。
特に、会社経営に関与していない親族にとっては、「価値がわからない」「換金できない」「責任を負いたくない」といった理由から相続放棄を選ぶケースもあります。
しかし、「相続放棄をすれば一切関係がなくなる」と考えるのは、少し危険です。非上場株式は、流動性や名義の問題から、相続放棄後にも関与を求められる場面があるのです。
本コラムでは、非上場株式を相続放棄した場合に生じうる事態と、その対策について、実務経験を踏まえて解説します。
1. 非上場株式とは?
非上場株式とは、証券取引所に上場されていない株式会社の株式を指します。主に中小企業や同族会社の株主が保有しており、その売買は限定的です。
上場株式との違い
上場株式は市場価格が明確で、証券会社を通じて簡単に売買できます。しかし、非上場株式は公開市場が存在しないため、
- ・株価がわからない(評価が難しい)
- ・売却先が見つかりにくい
- ・名義変更や譲渡制限の手続きが煩雑
といった特有の問題があります。
相続財産としては不透明な資産といえ、相続人にとって「扱いづらい財産」の代表例でもあります。
2. 相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産について、一切の権利義務を引き継がないという意思表示です。
相続放棄の基本ルール
- ・家庭裁判所への申述により行います(民法915条)
- ・原則として、相続開始(死亡を知った日)から3か月以内に手続きが必要
- ・放棄が認められると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます
放棄の効力は、すべての相続財産に及ぶため、プラスの財産(不動産・預金など)も受け取れなくなります。
3. 非上場株式を相続放棄したらどうなる?
放棄した人は株式を引き継がない
当然ながら、相続放棄をした人は、その非上場株式についても相続することはありません。株主にはなりませんし、株主としての権利義務もありません。
次順位の相続人に権利が移る
しかし、相続放棄によって消滅した相続権は、次の順位の相続人に移ります。
- 例:
- ・長男が放棄 → 次男が相続人になる
- ・子全員が放棄 → 被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移る
そして、この流れで誰かが相続すれば、その人が株主となります。
誰も引き受けないと「行き場のない株式」に
問題は、次順位の相続人も放棄を選び、誰も株式を引き受けないケースです。この場合、最終的には「相続人不存在」として、手続きを経て国庫に帰属することになります。
ただし、これは非常に手間と時間を要するため、会社側が株主不在という状態で困ることになります。
4. 相続放棄しても「株主」として名前が残る?
ここが最も注意すべきポイントです。
名義書換がされなければ「株主」として扱われる
会社法上、名義書換がされていない限り、「株主名簿に記載された者」が株主とされます。
つまり、相続放棄をしていても、名義が変更されていなければ、形式上は株主のままです。
放棄したのに責任を問われる?
- 形式的な株主として
- ・株主総会の招集通知が届く
- ・配当金の支払い通知が送られる
- ・議決権行使を求められる
- ・会社の債務保証や責任問題に関わる可能性も
といった「厄介な事態」が起こりえます。もちろん、実際に権利行使する義務はありませんが、放棄したにもかかわらず巻き込まれる感覚は、避けたいところです。
5. 実務上のトラブル事例
ケース1:放棄後も会社から連絡がくる
ある相続人が非上場会社の株式を放棄したにもかかわらず、株主名簿の更新がなされず、会社から定期的に通知が届き続けたケース。会社は「株主が誰かわからない」と困惑し、結局、法的手続きの協力を求められた。
ケース2:後順位の相続人が音信不通
相続人が全員放棄し、次に権利が移る兄弟姉妹が行方不明。会社としては名義書換ができず、持分の整理もできず、譲渡や増資の手続きが滞ってしまった。
ケース3:債務超過会社の株式が宙に浮く
債務超過状態の会社の株式を相続放棄したところ、誰も引き受けず、会社側も株主が確定できないまま時間だけが経過。清算手続きも難航し、従業員や取引先にも影響が及んだ。
6. 対策・アドバイス
(1)生前の整理が最も効果的
非上場株式のような扱いが難しい資産は、被相続人の生前に整理しておくことが理想的です。
- ・株式の売却(可能であれば)
- ・会社への譲渡
- ・社員持株会への移転
などの方法を検討しましょう。
(2)遺言書による指定
遺言書に「この株式は○○に相続させる」と明記しておけば、相続手続きがスムーズになり、放棄リスクも低減します。
(3)相続放棄後の名義書換の働きかけ
相続放棄をした場合でも、会社や他の相続人と協力して名義整理を進めることが重要です。必要であれば専門家を通じて後順位相続人の確認・手続き支援を行いましょう。
(4)専門家への相談を早めに
弁護士・司法書士・税理士・M&Aアドバイザーなど、非上場株式の扱いに詳しい専門家に早めに相談することで、余計なトラブルを防ぐことができます。
7. まとめ
非上場株式を含む相続財産に対して相続放棄をした場合、一見「自分には関係ない」と思いがちですが、
- ・名義書換がされないまま放置されると、形式上株主として扱われてしまう
- ・次順位相続人への承継や、会社側の対応によってはトラブルに巻き込まれる可能性がある
といった落とし穴が存在します。
放棄したから終わりではなく、名義・実務・後処理まで見通しておくことが肝要です。
非上場株式をめぐる問題は専門性が高いため、早い段階での対策・相談がトラブル回避の鍵となります。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)