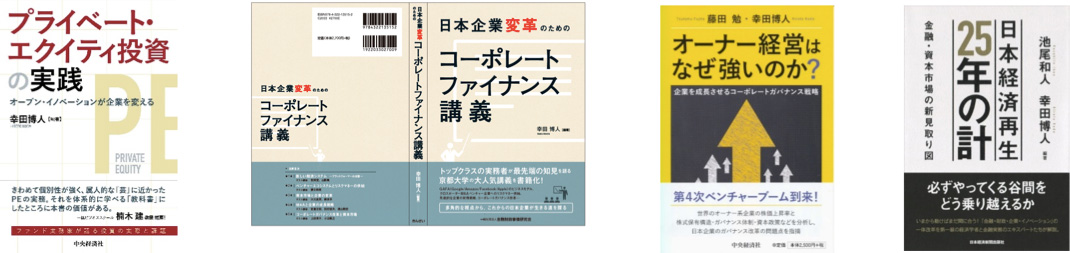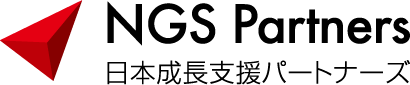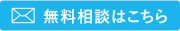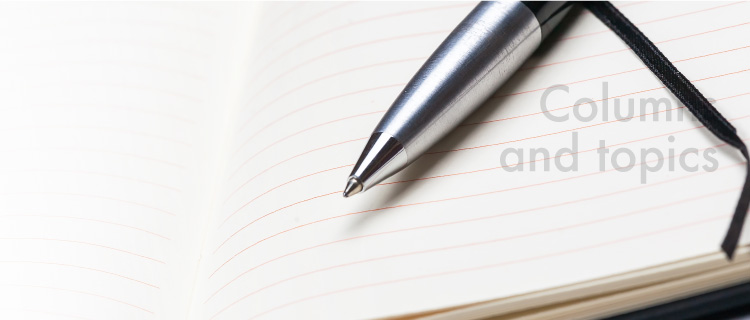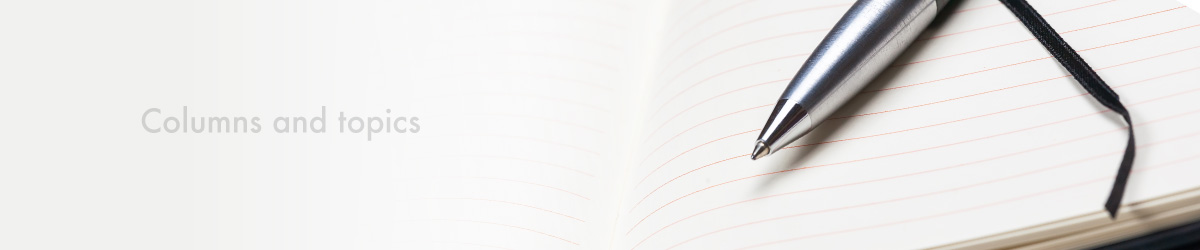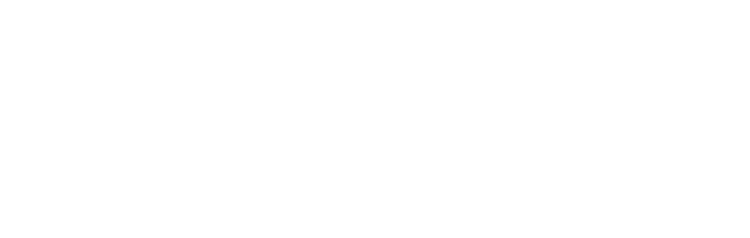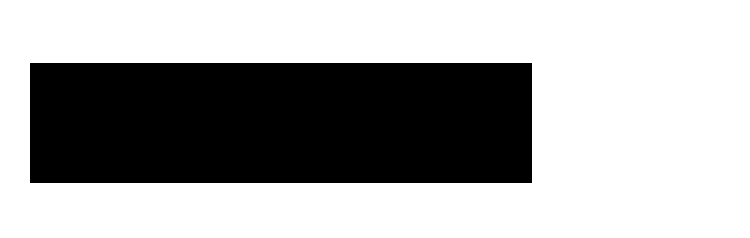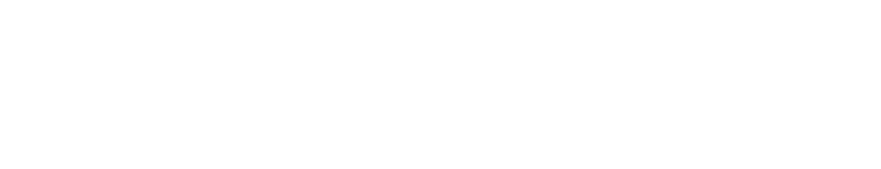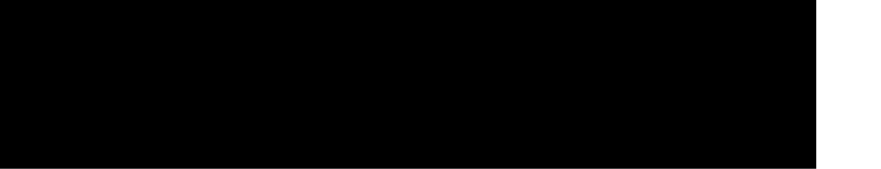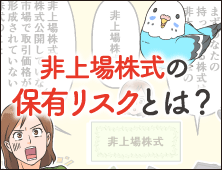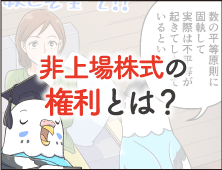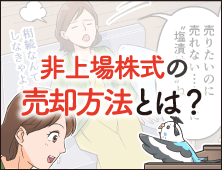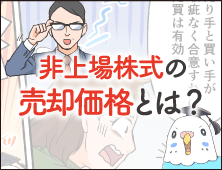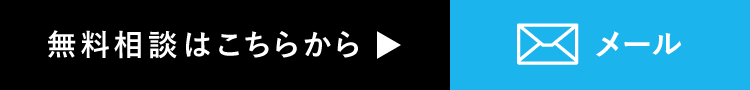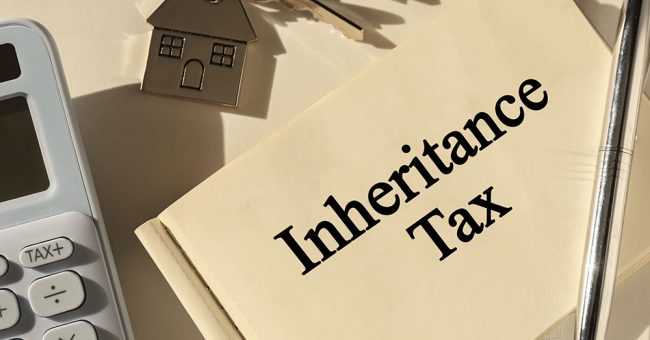
非上場企業の少数株式の売却支援をしていると、相続税とは切っても切れない関係にあることを実感します。特に、「株式の相続税評価額は高いのに、売ることができない = 納税のための資金が確保できない」といった悩みを抱える方は少なくありません。
相続税に関する情報は世の中にあふれていますが、節税テクニックや評価方法など、どうしても技術的な話題に偏りがちです。だからこそ今回は、相続税がそもそも何のためにあるのか、そして日本の制度は国際的に見てどのような位置にあるのかという、制度の根本に立ち返って考えてみたいと思います。
目次
1. 相続税ってどんな税金?
相続税は、誰かが亡くなって、その人の財産を受け継いだときにかかる税金です。現金や不動産、株式などが対象になります。
この税金には、大きく分けて2つの役割があります。
(1)富の再分配
特定の家庭や一族に富が集中しすぎないようにするための仕組みです。世代を超えて財産が偏ることを防ぎ、社会全体のバランスを保つ役割を果たします。
(2)所得税の補完
相続税は、所得税だけではカバーしきれない「富の移転」に対応する役割も担っています。具体的には次の2つの視点があります。
- ①例えば、生前に1億円分の株式を持っていた人が亡くなった場合、その株式はそっくり相続人に引き継がれます。相続人は自分で稼いだわけではありませんが、価値ある資産を手にすることになり、これは経済的に見ると「所得」とも捉えられます。このような場合、所得税ではなく相続税によって課税される仕組みになっています。
- ②株などの資産は、通常、売却して初めて利益が確定し、そこで所得税がかかります。ところが、売らずに保有したまま亡くなると、その利益(含み益)には課税されません。本来であれば課税対象となる富が、そのまま次の世代に移ってしまうことになります。こうした課税の抜け道を防ぐために、死亡時点で「一度清算した」とみなして課税するのが、相続税のもう一つの重要な役割です。
2. 二重課税ではないか?
よく「所得税と相続税の二重課税ではないか?」という疑問が挙がります。たしかに、亡くなった方がすでに所得税を支払った後の財産に、さらに相続税が課されるという点で「二重に取られている」と感じる方もいるでしょう。ただし、相続税は「富の移転」に対する課税であり、相続人にとっての「新たな取得」と捉える点で、税の性格が異なります。
3. 日本の相続税は重い?
日本では「三代で財産がなくなる」と言われることがあります。その背景にあるのが、非常に高い相続税率と小さな控除額(非課税枠)です。
日本の相続税の最高税率は55%。これはG7の中でもっとも高く、さらに控除額(非課税枠)が小さいため、比較的資産の少ない家庭でも課税対象になってしまいます。
つまり、日本の相続税制度は「富裕層課税」ではなく、むしろ「中間層課税」とも言える設計になっています。
4. G7各国との相続税比較
以下に、G7各国における相続税の概要を、日本円換算も交えてまとめました(為替は1ドル=150円、1ユーロ=160円、1ポンド=190円で換算)。
表からも分かるように、たとえばアメリカでは、控除額が約20億円と非常に大きいため、相続税がかかるのはごく一部の富裕層に限られています。
| 国名 | 控除額(現地通貨) | 控除額(日本円換算) | 最大税率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 | 例:相続人2人なら4,200万円 | 55% | 中間層でも課税対象に |
| アメリカ | 約1,360万ドル | 約20.4億円 | 40% | 富裕層のみ課税対象 |
| イギリス | £325,000(自宅含むと最大£500,000) | 約6,200万円〜9,500万円 | 40% | 自宅に追加控除あり |
| フランス | €100,000/子 | 約1,600万円 | 最大45% | 血縁関係によって変動 |
| ドイツ | €400,000/子 | 約6,400万円 | 最大30% | 家族に手厚い控除 |
| イタリア | €1,000,000/子 | 約1.6億円 | 最大8% | 控除が大きく税率も低い |
| カナダ | なし(相続税制度なし) | - | - | 死亡時の資産に譲渡益課税のみ |
(出典)・OECD(2021)『Inheritance Taxation in OECD Countries』 ・財務省『主要国における相続税負担率の比較』(2025年1月現在) ・Tax Foundation「Top Estate or Inheritance Tax Rates to Lineal Heirs in the OECD」
5. なぜ日本はここまで課税が重いのか?
一つの背景にあるのが、「クロヨン」と呼ばれる税負担の不均衡です。
給与所得者(サラリーマン)は税務署に収入を正確に把握されやすく(ク:9割)、 一方で、自営業者(ロ:6割)や農家(ヨン:4割)は経費などで所得を操作しやすいため、正確に把握されにくいという実態があります。
その結果、「見えるお金」に対して確実に課税するために、相続税が重要な位置づけを担ってきたという経緯があります。
6. マイナンバー制度と「見えるお金」
近年、マイナンバー制度の導入により、金融資産・不動産・証券口座などの情報を国が把握しやすくなっています。これにより、従来は把握困難だった資産も「見える化」されつつあります。
その結果、「もう所得を正確に補足できるなら、相続税はいらないのでは?」という意見も一部に見られますが、これはあくまで理想論に近く、現実には依然として資産の偏在や評価の困難さが課題として残ります。
7. 相続税ゼロの国はどうしてる?
G7ではカナダが相続税制度を持たず、代わりに死亡時点での譲渡益に対して課税する「みなし譲渡課税」を採用しています。
さらに、オーストラリア、スウェーデン、スイス(連邦レベル)なども相続税を廃止しています。
- これらの国では、
- ・所得課税が徹底されている(補足率が高い)
- ・国民的に税への理解と納得がある
- ・社会保障制度との整合性がとれている
など、背景には複合的な要因があります。
8. まとめ 〜税金は社会を支えるしくみ
相続税は「お金を取られる嫌な制度」ではなく、社会全体で公平を保つためのしくみです。
とはいえ、日本の制度は高税率・低控除という特徴があり、課税対象が中間層にも及ぶことで、さまざまな問題も生じています。
非上場株式を相続する方にとっては、「納税資金の確保」が現実的な課題になります。そのため、税制の本質を理解し、早めに対策を講じることが重要です。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)