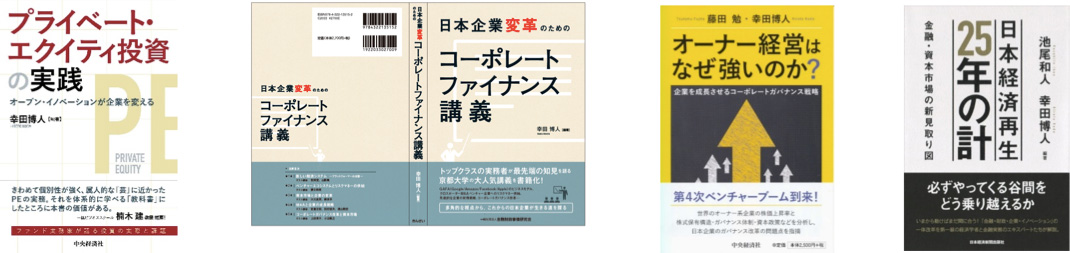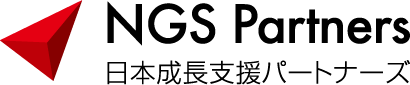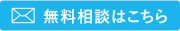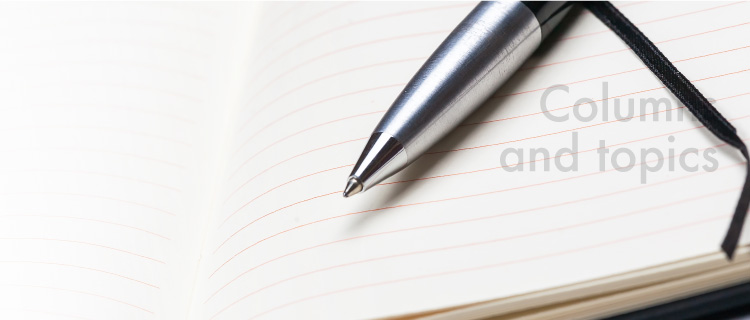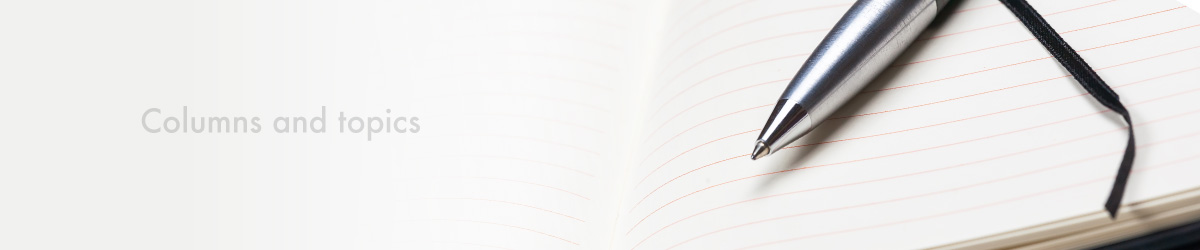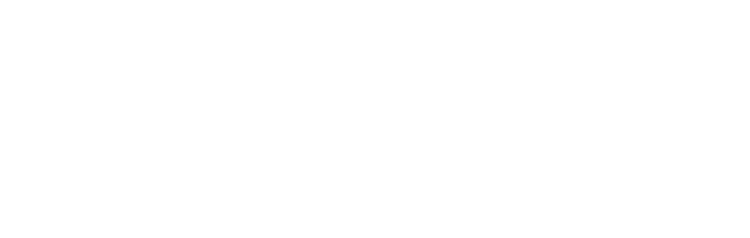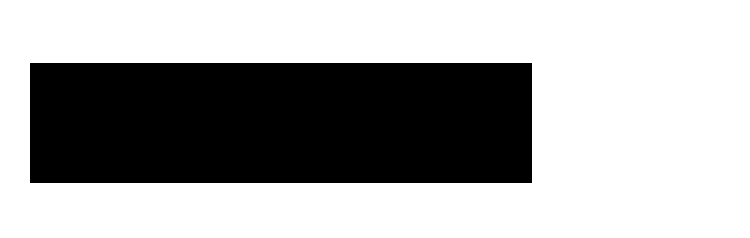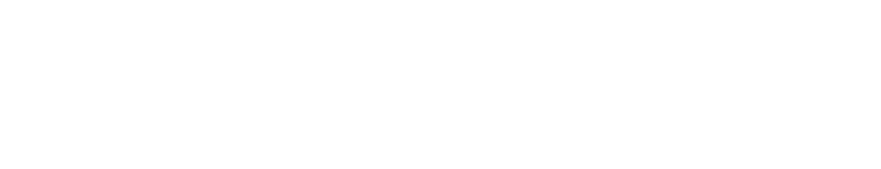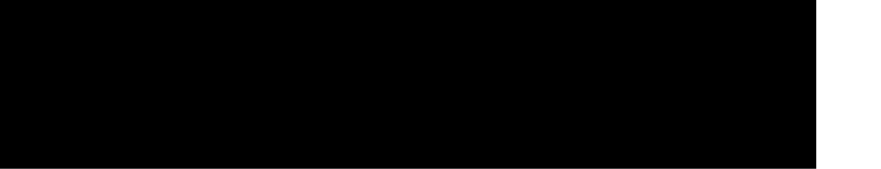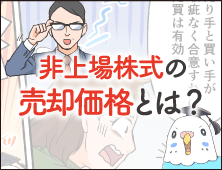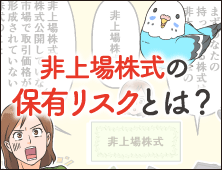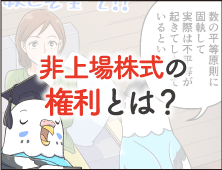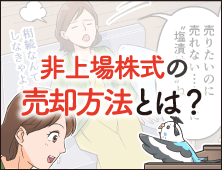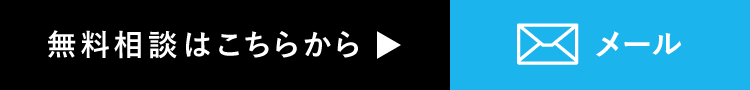同族会社の個人株主が保有する非上場株式を売却するとき、「税務上の時価」や「みなし贈与」「みなし譲渡」「みなし配当」など、普段あまり聞き慣れない専門用語が次々と出てきて、戸惑う方も多いのではないでしょうか。この記事では、同族会社の個人株主が非上場株式を売却する際の税務上のポイントと注意点をわかりやすく解説します。
目次
1.「税務上の時価」とは?
「時価」という単語は、一般的には「今の市場で売ればいくらになるか」という意味で使われますが、税務の世界では少し違う意味を持ちます。「税務上の時価」とは、相続や贈与、あるいは株式の売買などにおいて、課税の基準となる金額を指します。特に非上場株式(市場に出回っていない会社の株式)では、株式の値段が決まっていない(取引相場が決まっていない)ため、国が示す一定のルールに従って「時価」を計算する必要があります。
この計算方法には、「配当還元方式」や「純資産価額方式」「類似業種比準方式」などがあり、株主の立場や会社の規模などによって使い分けられます。たとえば、実際の取引価格がこの「時価」より著しく低い場合(低額譲渡された場合)、税務署から「差額は贈与に該当する」と判断され、贈与税が課されることもあります。
つまり、「税務上の時価」とは、税金を計算するために国が定めた“公正な価格”であり、実際の売買価格とは異なることがある点に注意が必要です。
ポイント
「税務上の時価」とは、課税の基準となる金額
2.非上場株式は、税務上の「時価」で取引しないといけないの?
そんなことはありません。非上場株式を売却する場合、民事上は当事者同士の合意があれば、価格はいくらであっても構いません。たとえば、1株1円でも1億円でも、当事者間で契約が成立すれば有効です。ただし、税務上は別です。
税務上は、たとえ当事者が納得していても、その取引が「時価」に基づいて行われていない場合には、贈与や譲渡益の否認といった課税リスクが生じる可能性があります。特に、親族や会社関係者など「特殊関係者」との取引は、実質的に利益の移転とみなされる可能性があります。
一方で、純然たる第三者(利害関係のない他人)間において、種々の経済性を考慮して定められた売買の場合は、その取引価格が「時価」として税務上も認められる可能性が高くなります。つまり、「誰とどのように取引するか」によって、税務上の扱いが大きく変わる点に注意が必要です。
ポイント
非上場株式の譲渡における「時価」は、純然たる第三者間取引であるか否かで変わる。
3.同族会社の個人株主が保有する非上場株式を売却するときの課税関係
ここでは、次の3つのケースについて、親族や会社関係者など「特殊関係者」が、税務上の時価で取引した場合と、時価より著しく低い価格で取引した場合(低廉譲渡した場合)とで、どのような課税関係が生じるのかを整理してみます。
- (1)売り手:個人、買い手:個人
- (2)売り手:個人、買い手:法人(発行会社以外)
- (3)売り手:個人、買い手:法人(発行会社による自己株式の取得)
(1)個人から個人への売却
①税務上の時価で取引した場合
通常の譲渡所得課税が行われます。
- ・売り手(譲渡する個人)には、譲渡所得税(所得税+住民税)が課税されます。
→ 譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)
→ 税率は 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
- ・買い手(個人)には、特に税金は課されません。
→ 正当な対価を支払っているため、贈与税などは発生しません。
このように、「税務上の時価」での譲渡であれば、課税はシンプルであり、トラブルも起きにくいです。
②低廉譲渡した場合
買い手に「みなし贈与」課税のリスクが生じます。
- ・買い手に「みなし贈与」課税が発生する場合であっても、売り手(譲渡する個人)は影響を受けず、(1)①の場合と同様、通常どおり譲渡所得税が課税されます。
- ・買い手(個人)は、時価と実際の譲渡価格の差額について、贈与を受けたものとみなされ、贈与税(みなし贈与課税)の対象になります。
→ 例えば、時価1,000万円の株式を100万円で買い取った場合、差額の900万円について贈与税が課税される可能性が高いです。
③みなし贈与とは?
「みなし贈与」とは、実際には「タダでもらった」とは言っていなくても、実質的には「タダでもらったのと同じだよね」と税務署が判断することです。言い換えると、「見かけは普通の取引でも、実質的に贈与と変わらないよね」と税金上はみなされて、贈与税がかかるという仕組みです。(相続税法7条)
なお、国税庁ホームページ(No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき)には、次のように記載されています。
「個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。」
(2)個人から法人(発行会社以外)への売却
①税務上の時価で取引した場合
通常の譲渡所得課税が行われます。
- ・売り手(譲渡する個人)には、譲渡所得税(所得税+住民税)が課税されます。
→ 譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)
→ 税率は 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
- ・買い手(法人)には、特に税金は課されません。
②低廉譲渡した場合
売り手には「みなし譲渡」課税が生じ、買い手は時価と実際の取得価額との差額が課税対象となります。
- ・売り手(譲渡する個人)には、「みなし譲渡」課税が生じます。
- ・買い手(発行会社以外)には、法人税法上、買い手法人が時価より著しく低い価額で株式を取得した場合、その時価と実際の取得価額との差額は「受贈益」(無償の経済的利益)として、法人所得に計上され法人税が課されます(法人税法22条)。
③みなし譲渡とは? / 個人間の売却では生じなかった「みなし譲渡」課税が、個人-法人間では生じる背景
「みなし譲渡」とは、個人から法人に対して資産が低廉譲渡された場合、実際の取引価格にかかわらず「時価で譲渡したもの」とみなされ、税金を課すという仕組みのことです(所得税法59条)。
これは、法人は原則として存続期間に制限がなく(個人のように死亡による資産の引き継ぎが発生せず)、個人が資産を法人に移してしまえば、その資産を売却しない限り課税されず、結果として税金の繰り延べ、さらには回避が可能になってしまう恐れがあるためです。そのような不適切な節税を防ぐために、「みなし譲渡」課税という制度が設けられています。
(3)個人から法人(発行会社)への売却(自己株式の取得)
①税務上の時価で取引した場合
売り手に「みなし配当」課税が生じます。
- ・売り手(譲渡する個人)には、譲渡所得税(所得税+住民税)が課税されます。
→ 譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)
→ 税率は 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
ただし、譲渡収入のうち、「対価の額」が「資本金等の額」を超える部分については、利益積立金額の払戻しに相当すると考え、「みなし配当」として課税されます。
- ・買い手(法人)には、特に税金は課されません。
②低廉譲渡した場合
- ・売り手(譲渡する個人)には、上記(3)①の譲渡所得課税・みなし配当課税に加えて、税務上の時価と対価の差額について、みなし譲渡課税が発生する可能性があります。
- ・買い手(発行法人)は、自己株式の取得となり、法人税課税は発生しません。
- ・発行法人の株主(既存株主)には、みなし贈与税が課される可能性があります。これは、同族経営の会社(経営者やその家族が大株主である会社)に、経営者やその親族がタダ同然(無償または非常に安い価格)で財産を渡した場合、会社の財産が増えることで株式の価値も上がります。すると、その株を持っている経営者や親族が、結果として「得」をしますよね?この「得」を、税務上は「株主が贈与を受けた」とみなして、贈与税がかかる場合があるということです。
③みなし配当とは?
通常、配当とは法人が利益を株主に分配する行為ですが、「みなし配当」は形式的には配当でなくても、実質的に株主に対して利益の分配が行われたとみなされるケースに適用されます。
株式の自己取得(いわゆる自己株式の買戻し)において、取得価額がその株式の資本金等の額を上回る部分については、配当と同様の課税関係が生じます。特に著しく低い価格での譲渡では、その差額が「本来の株主(=個人)に還元された」と見なされ、みなし配当として所得税の対象となるのです。
所得税は超過累進課税となっており、課税所得(給与所得などから控除を差し引いた後の金額)に応じて5%から最大45%までの税率が適用されます。
さらに、住民税は一律10%が課されるため、所得税と住民税を合わせると、最大で55%の税率となる場合があります。
4. まとめ
非上場株式を売却する際に、「税務上の時価」を意識せずに取引してしまうと、後になって思わぬ課税を受けることになりかねません。
誰が誰に、どのような価格で株式を売却するのかによって課税関係は大きく変わるため、事前に専門家のアドバイスを受けながら、慎重に手続きを進めることが重要です。
後から慌てることのないよう、必ず事前の確認を行いましょう。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)