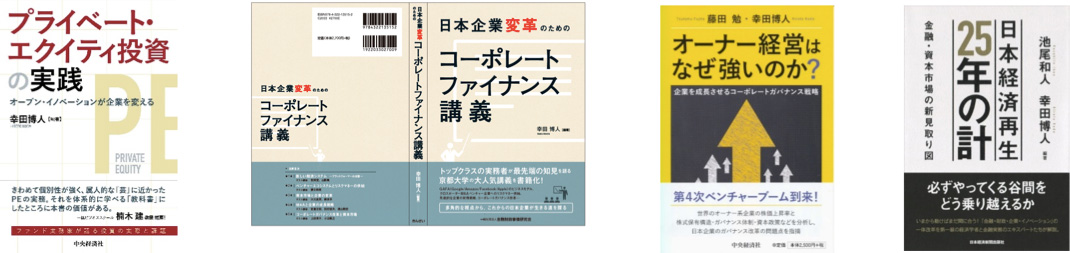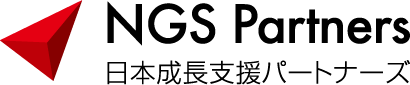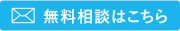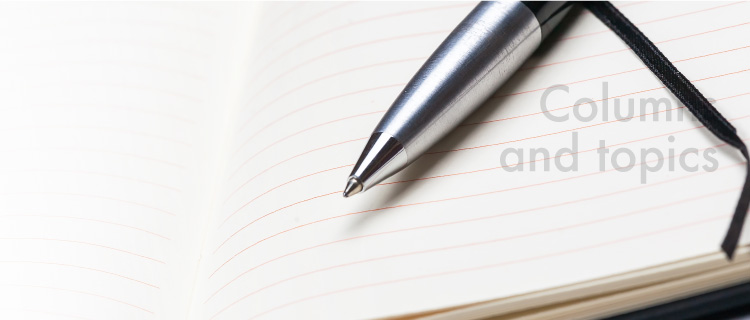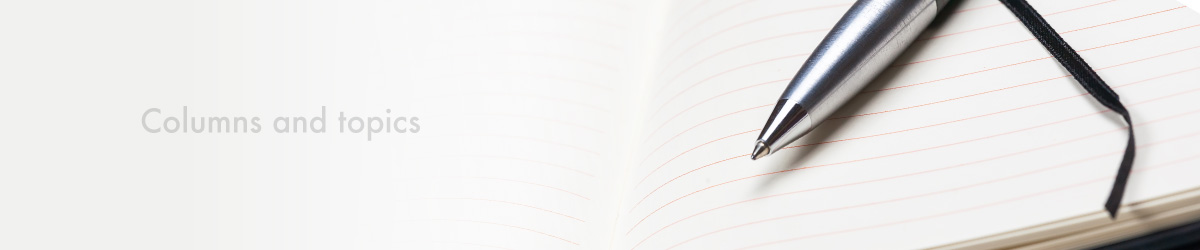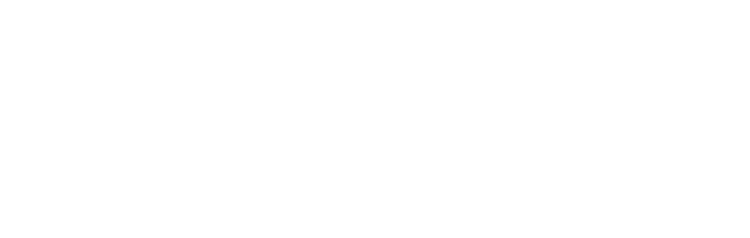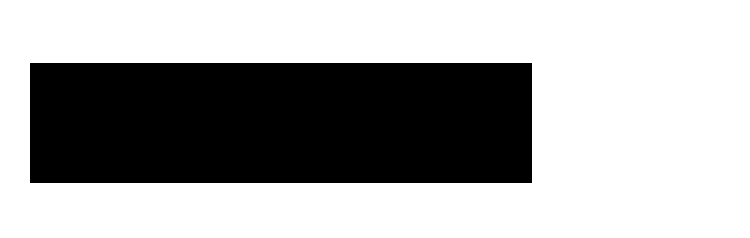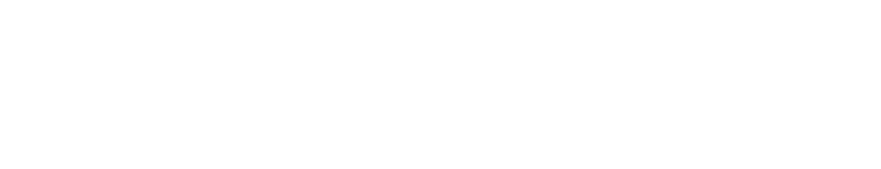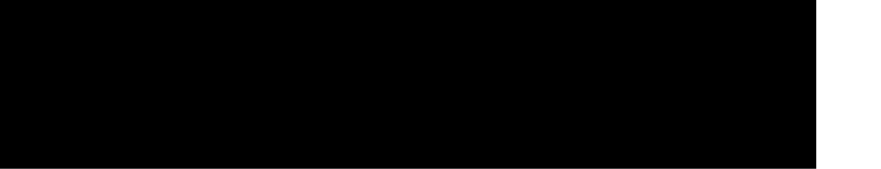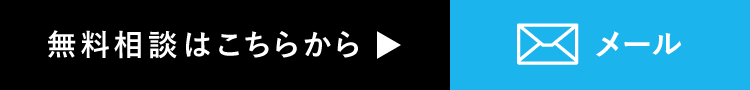中小企業や非上場会社では、オーナーやその親族が株式を保有しているケースが一般的です。こうした会社が税務上の「同族会社」に該当するかどうかは、税務処理や取引スキームの設計に大きな影響を及ぼします。
特に見落とされがちなのが、「法人株主」が同族関係者として扱われるケースです。形式上は法人でも、実質的にはオーナーやその親族の支配下にあると判断されると、「同族株主」とみなされ、税務上の制約やリスクが発生します。
このコラムでは、専門家はもちろん、「自分や自分の会社が同族会社に該当するのか知りたい」という非専門の方にも分かりやすく、「法人株主」の扱いに関する基本的な考え方と注意点を解説します。
目次
1. 同族会社とは? ── 税務上の定義
まず「同族会社」という言葉は、税務上の用語です。法人税法第2条第10号では、以下のように定義されています:
株主等のうち特定の者(オーナーや親族などのグループ)が、発行済株式の50%超を保有している会社
つまり、以下のような構成であれば「同族会社」とみなされます:
- ・社長本人が40%、その妻が10%、子が10%保有 ⇒ 合計60% → 同族会社
ここで重要なのが、「法人株主」も、この“同族グループ”に含まれる可能性があるという点です。
2. 法人株主が「同族関係者」とみなされるケース
法人株主が「同族株主」とされるのは、主に以下のような場合です。
- ケース① オーナーが100%出資する資産管理会社が株主
- → 出資者(オーナー)と法人が一体と見なされ、法人も「同族株主」にカウントされます
- ケース② 親族が出資・役員を兼ねる別法人が株主
- → 出資割合や経営支配の度合いによっては、「実質的にオーナー支配下」と判断されます。
- ケース③ 名義上は別法人でも、実態としてオーナーが実権を持っている
- → 税務署は形式ではなく実態を重視します。「オーナーの言いなりになっている法人」は、同族関係者とみなされるリスクあり。
3. よくある誤解とリスク
- 「うちは親族が株主じゃないから大丈夫」?
- → 表面的に親族名義でなくても、法人がオーナーの資産管理会社であれば同族関係とされます。
- 「法人は別人格だからカウントされないのでは?」
- → 法人であっても、実質的な支配関係があれば「同族関係者」として扱われます。
そして、税務調査で問題になると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- ・寄附金認定(損金不算入):法人間での不自然な価格設定による利益移転と判断される場合
- ・受贈益課税:相手法人に思わぬ課税が発生するケースも
- ・株式移動の否認:実質支配の継続があると見なされ、譲渡が無効扱いとなるおそれ
こうした事態は、税負担だけでなく信頼関係の悪化やレピュテーションリスクにもつながるため、事前の対策が重要です。
4. 実務での注意点と対応策
実務上は、以下のような観点からリスクを洗い出し、慎重に対処することが求められます。
- ・株主構成を形式でなく“実質”で見直す:名義上の株主だけでなく、支配構造を俯瞰的に把握しましょう。
- ・法人株主の背後関係を確認する:出資者や役員構成、実質的な支配権者がオーナー一族でないかをチェック。
- ・資産管理会社・持株会社が関与する場合は要注意:これらは特に“形式上は別人格、実質はオーナー”と見なされやすい存在です。
- ・不安がある場合は専門家に事前相談を:税理士・会計士による第三者の視点で、リスクの棚卸しを行うことをおすすめします。
税務上の「同族会社」該当性は、後になってから問題になることが多く、早めのチェックと備えが肝要です。
5. 同族会社に該当することで生じる主な税務的影響
「同族会社」に該当すること自体が違法・不利というわけではありませんが、該当することで特有の税務上の取扱いや制約が生じる点には注意が必要です。以下のような点が、実務上とくに影響を与える場面です。
- ・留保金課税の対象になる可能性: 一定の利益を社内に留保している同族会社には、「留保金課税(留保所得課税)」が適用される場合があります。これは会社内部に利益を溜め込み、オーナーの所得を意図的に繰延べているとみなされることによる追加課税です。
- ・寄附金の損金算入限度が厳しくなる: 同族会社が関係会社やオーナー関連法人に対して行う寄附や支出について、税務上「寄附金」として損金不算入とされる可能性が高まります。
- ・役員給与や退職金の税務調整がシビアに: 役員報酬や退職慰労金の額が過大であると判断されれば、その一部が損金に算入されず、課税所得が増える結果となります。とくにオーナー一族に対する支給は厳しくチェックされます。
- ・税務調査の対象になりやすい: 同族会社は、「オーナーの意向で取引が決まる」「経済合理性よりも個人都合が優先されがち」といった懸念から、税務署の調査対象として優先的に選ばれる傾向があります。
こうした影響を最小限に抑えるには、適切な利益配分や契約整備、取引の透明性確保が不可欠です。
6. まとめ
法人株主だからといって安心はできません。税務上は「実質的な支配関係」に基づいて判断されるため、形式的に別法人であっても、オーナーと一体と見なされれば「同族関係者」とされ、会社全体が「同族会社」に該当する可能性があります。
特に持株会社や資産管理会社を使った株式保有をしている方は、一度その関係性を整理しておくことをおすすめします。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)