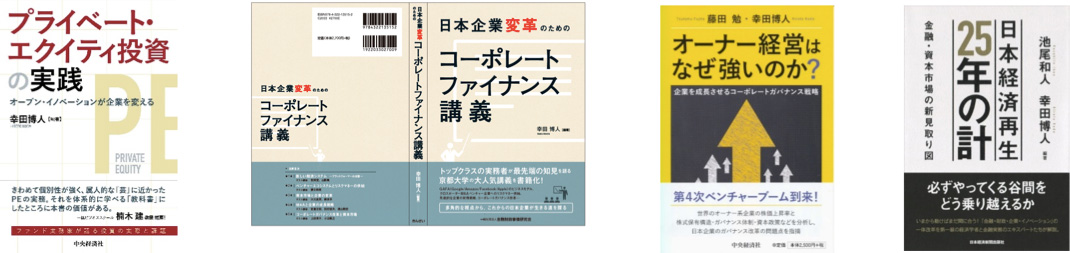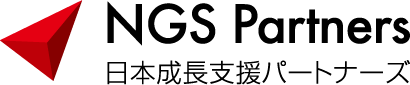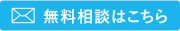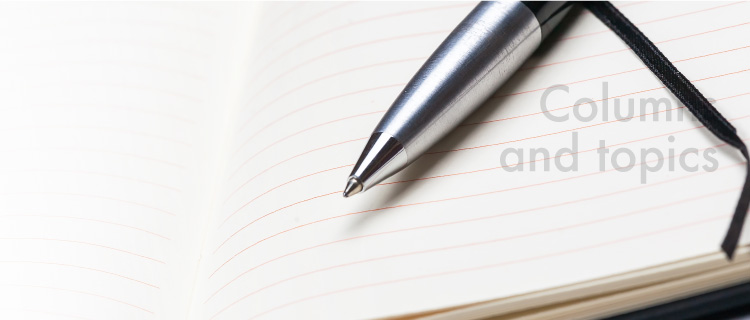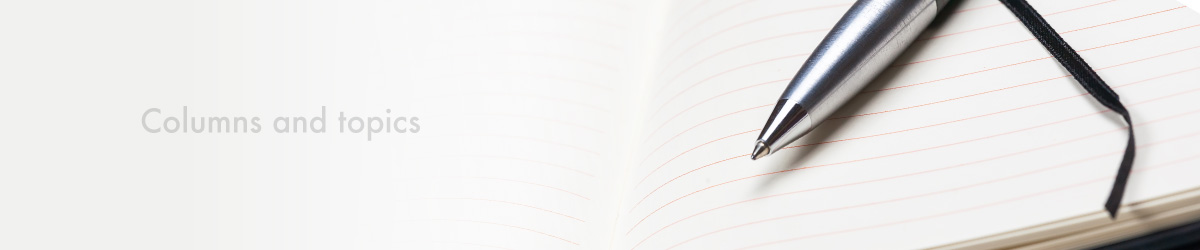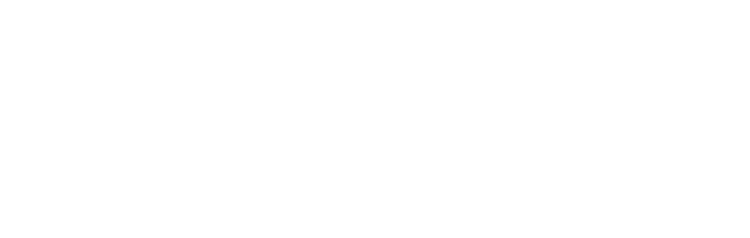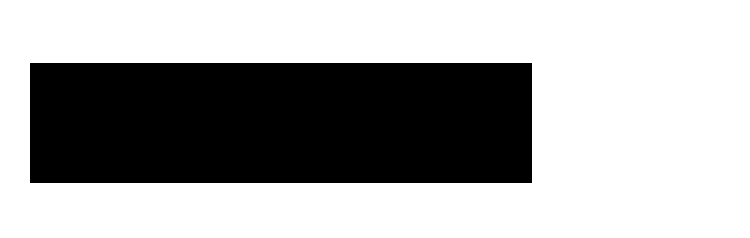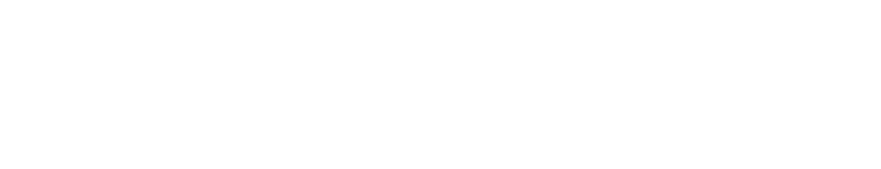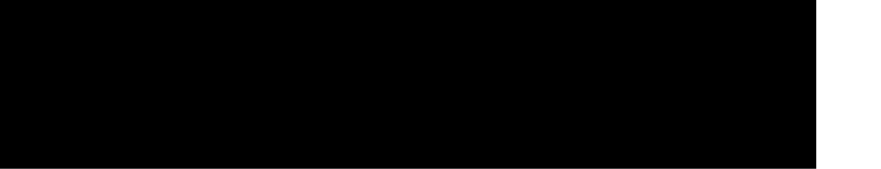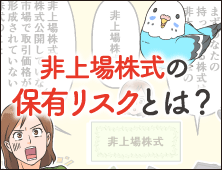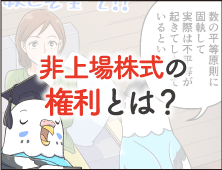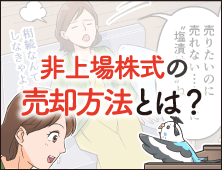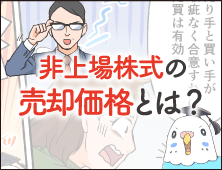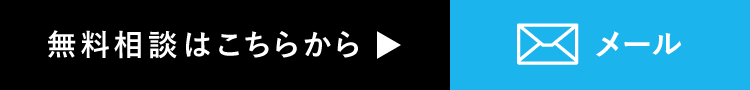会社法を遵守している企業であれば、たとえ非上場の同族会社であっても、株主には通常、年に1回は「株主総会招集通知」(以下、招集通知)が送付されます。これは、上場・非上場を問わず、同族会社を含むすべての株式会社において、会社法により、株主総会の開催とそのための招集通知送付が義務付けられているからです。
この記事では、この招集通知がどのような意味を持ち、特に非上場・同族会社の株式を売却する時にどのような役割を果たすのかを詳しく解説します。
目次
1.招集通知とは
「招集通知」とは、会社が株主に対して株主総会の開催を通知し、議題や日時・場所などを記載した公式文書です。会社法では、公開会社(上場企業)の場合は、株主総会の2週間前まで(非公開会社(非上場企業)の場合は、1週間前まで)に株主へ送付することが定められており、同封資料として事業報告、計算書類(貸借対照表・損益計算書など)が含まれるのが一般的です。
特に非上場企業においては、上場企業に比べて、公開されている情報が限られているため、この一通の招集通知から得られる情報は非常に重要です。
2.非上場企業でも「招集通知」は存在する
招集通知は「上場企業の株主だけが受け取るもの」と思われがちですが、実際には会社法により非上場企業でも招集通知の送付が義務づけられています。
特に同族会社においては、株式の大半を創業者一族が保有しているケースが多く、その他の株主(たとえば元従業員や相続によって株式を取得したが経営に関与していない親族など)は、会社の実情を知る手段が限られています。そうした状況で、招集通知は会社の経営状況を理解するための貴重な資料になります。
3.招集通知にはどんな情報が含まれているのか?
招集通知には以下のような情報が含まれています。
- ・株主総会の日時、場所
- ・会議の目的事項(議題)
- ・事業報告の概要
- ・貸借対照表・損益計算書
- ・配当の有無・金額
- ・役員選任や報酬に関する議案
これらの情報から、会社がどのような方向に向かっているのか、業績は好調か、資産の健全性は保たれているかなど、ある程度の把握が可能です。
4.株主総会とセットで理解すべき
招集通知は単なるお知らせではなく、株主総会という会社の最高意思決定機関への招待状です。非上場企業においても、株主は経営の重要事項に対して議決権を行使する権利を持ちます。
しかし、非上場企業の実情として、特に親族経営が中心の同族会社では、ガバナンスが形骸化しがちで、株主総会が開かれない、あるいは「いつの間にか開催されたことになっていた」といったケースも見受けられます。仮に開催されても、議論らしい議論が行われず、形式的に終わってしまうことも少なくありません。それでも、招集通知が届き、株主総会が正式に開かれるのであれば、株主として参加することには大きな意義があります。
5.非上場株式の売却を検討する際、なぜ招集通知が重要なのか?
非上場株式の売却を検討する際、買い手にとって重要となるのは、会社の実態です。すなわち、「どのような事業をしていて、どれだけの利益が出ており、将来性があるのか」といった情報です。
その判断材料として、招集通知や同封資料は数少ない公的情報となります。株価を検討する上でも、業績や財務内容、事業内容などが確認できる招集通知は、極めて重要な資料です。特に、会社の内情にアクセスしづらい非上場企業の少数株主にとっては、こうした資料が数少ない情報源となるため、その重要性は一層高まります。
加えて、招集通知を送付し、株主総会を開催しているという事実そのものが、経営陣に「株主と向き合う意思がある」という姿勢を示すサインになります。これは、会社との対話を重視する買い手候補にとって、安心材料となり得る点でも見逃せません。
なお、招集通知は、売却を検討している売り手だけでなく、買い手にとっても会社の価値やリスクを判断するために重要な資料です。そのため、届いた招集通知は捨てずに、紙のままで保管するか、スキャンしてデータとして保存しておくことを強くおすすめします。買い手から、売却時に過去の招集通知の確認を求められることもあるため、事前に準備しておくと安心です。
6.株主総会に出席しない場合も「招集通知」は読むべき
時間的・地理的な都合で株主総会に出席できないとしても、招集通知を読み込むことによって、会社に対する理解を深めることは可能です。議案の背景や役員の選任方針、財務状況などに目を通すことで、「売却すべきかどうか」「どのタイミングが良いか」の判断材料になります。
実際、株主総会に出席していないものの、通知の情報をもとに株式売却の問い合わせをいただく株主も少なくありません。
7.株主総会では揉める必要はない
一部の株主にとって、株主総会は「会社に意見をぶつける場」と捉えられがちです。しかし、実際には会社と対立するための場ではなく、建設的な関係性を築くための貴重な接点と考えるべきです。
株主とは、「会社の一部を所有する者」であり、「敵対する存在」ではありません。むしろ、会社をともに支えていく立場であり、経営を応援する存在であるべきです。
株主総会に出席すれば、ふだん接点のない経営陣の「生の声」に触れることができ、紙面だけでは読み取れない温度感や考え方を知ることができます。また、今後の経営方針について、経営者の口から直接説明を受けることで、会社の方向性やスタンスをより深く理解することができます。
さらに、株主として顔を出すことで、経営陣に自身の存在や姿勢を知ってもらうきっかけにもなります。そうした信頼関係の積み重ねは、将来的な株式売却や交渉の場面でもプラスに働く可能性があります。
たとえ将来的な株式売却を想定している場合でも、まずは冷静に会社の情報を収集し、自身の選択肢を整理することが大切です。株主総会は、その第一歩となり得る機会です。
8.まとめ ー 非上場株式の売却を考えるなら、「招集通知」は必ずチェック
非上場企業の株主にとって、招集通知は数少ない「会社との接点」です。株主総会に出席するか否かにかかわらず、まずは通知を丁寧に読み解くことで、会社の状態を知り、将来の売却や承継を見据えた意思決定に役立てることができます。
特に、「非上場株式の売却」や「同族会社における株式の売却」を検討している場合には、招集通知に記された情報こそがスタートラインです。
“知らずに売る”のではなく、“理解した上で選ぶ” ── それが納得できる売却につながります。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)