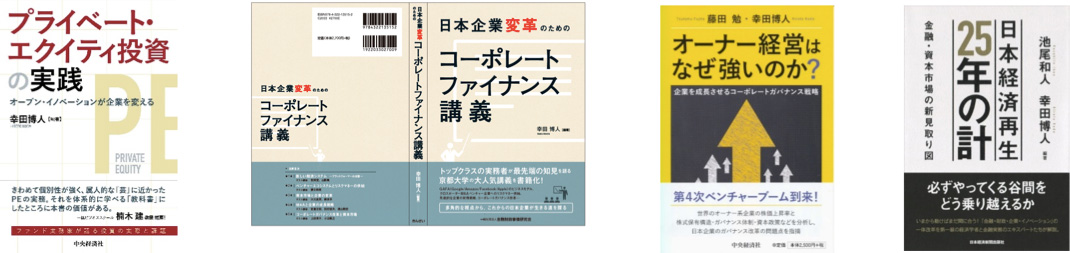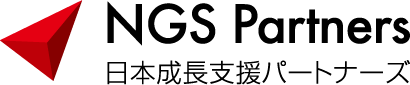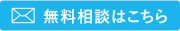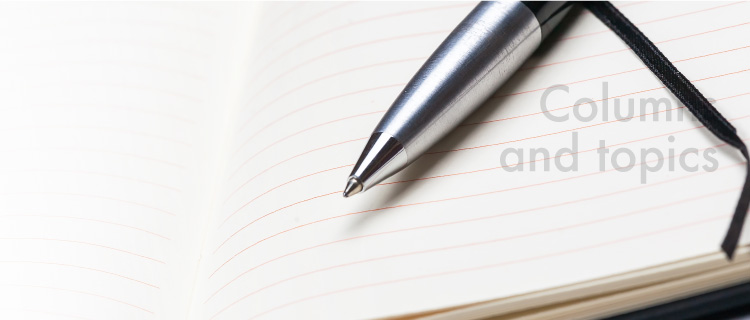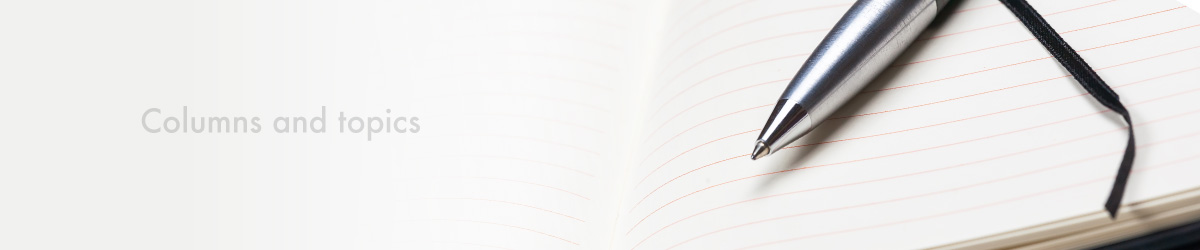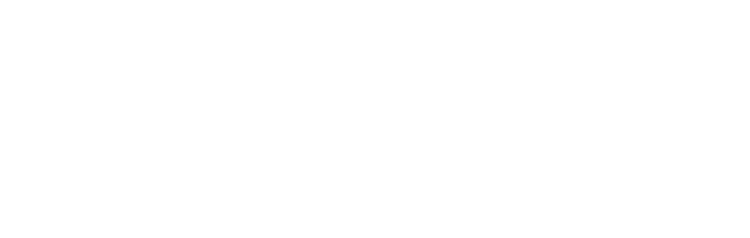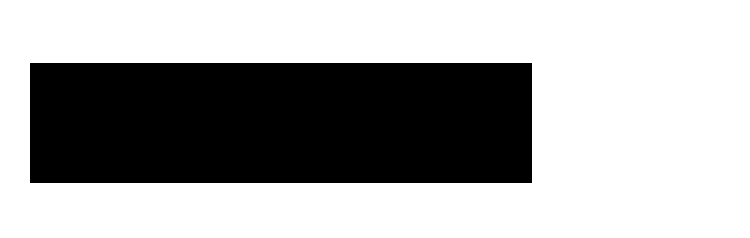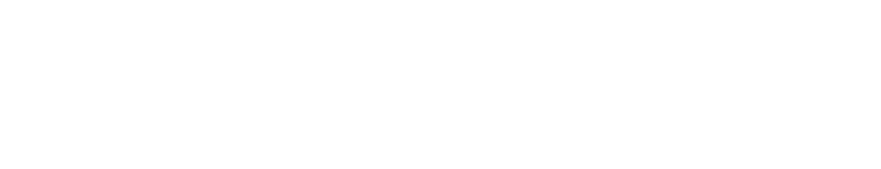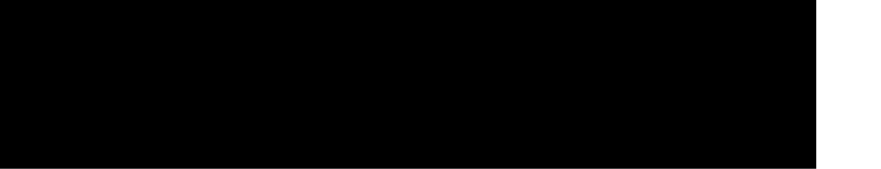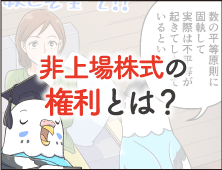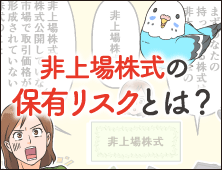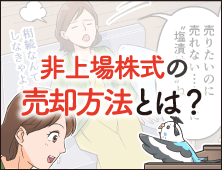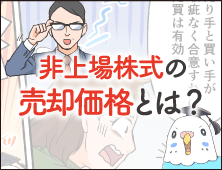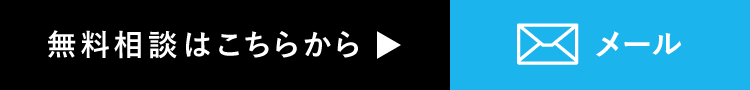中小企業の経営や事業承継において、「同族会社」という言葉を耳にする機会は少なくありません。経営者の多くが親族や近親者の間で株式を保有し、実質的な経営権を家族内で維持している会社は、実態として非常に多く存在します。
近年では、後継者不足や相続に関する問題が深刻化しており、同族会社の運営体制やガバナンスが改めて注目されるようになっています。また、非上場株式の相続税評価や、少数株主との関係性といった法的・税務的な論点が実務上の課題として浮上することも増えています。
このコラムでは、同族会社の基本的な定義や仕組みを確認したうえで、そのメリット・デメリット、さらには少数株主との関係性が持つ意味やリスクについて、実務的な観点から整理していきます。
1. 同族会社とは
同族会社とは、一般的に特定の親族や関係者が会社の支配権(議決権)を保有している会社を指しますが、その定義は法律上も明確に定められています。
法人税法第2条第10号においては、「同族会社」とは、「会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保有している会社」を意味します。
具体的に「特殊な関係にある個人や法人」とは、以下のとおりです。
- 1. 株主等の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)
- 2. 株主等と事実上の婚姻関係にある者
- 3. 株主等の使用人
- 4. 株主等から受ける金銭やその他の資産により生計を立てている者
- 5. 株主等並びに株主等と特殊関係のある個人及び法人で他の会社を支配している場合の当該他の会社。なお、支配しているとは、発行済株式又は出資の50%超を所有している他の会社をいう。
つまり、経営者個人が大株主であるだけでなく、親族や関連法人を含めて議決権の過半数を保有している場合、法律上「同族会社」として扱われます。
このような会社は、企業規模に関係なく該当し得る点が重要です。売上数百億円規模の企業であっても、議決権の構成が上記要件に合致すれば同族会社に分類されるため、税務やガバナンスの点でも特有のルールが適用されます。
実際、日本の中小企業の大多数がこの「同族会社」に該当するといわれており、経営者の意思が迅速に反映されやすい反面、透明性や外部評価の観点で課題を抱えるケースも少なくありません。
2. 同族会社のメリット
同族会社は、特定の株主グループによって経営権が集中しているという構造上、意思決定の迅速さや柔軟性といった点で大きなメリットを有しています。以下に代表的な利点を紹介します。
(1)迅速な意思決定が可能
通常の会社であれば意思決定に向け多くのプロセスが必要になりますが、同族経営の場合、経営者を含めて、関わりが深い人間のみが経営権を握っており、迅速な意思統一が可能です。「経営権の寡占」とネガティブに捉えられる場合もありますが、経営にスピード感が求められる昨今、ポジティブな側面もあると考えられています。
(2)経営の安定性と長期的視点の確保
同族会社は、安定した経営で長く存続する企業が多いと言われています。その背景には、経営者を含め、関係の深い人たちの間で経営が行われるため、「会社を永続させたい」という意識が自然と高まる点があります。特に、同じ経営者が長期間にわたって会社を率いるケースが多く、一貫した経営方針のもとで、長期的な戦略を実行しやすい環境が整っています。
さらに、外部株主に対する短期的な利益還元のプレッシャーが比較的少ないため、将来を見据えた投資判断や事業展開、ブランド価値の育成など、長期的な視点に立った経営が可能です。こうした特徴は、同族会社ならではの強みです。
(3)事業承継が比較的スムーズ
経営者の親族が株式とともに経営権を引き継ぐケースが多いため、円滑な事業承継が行いやすいのもメリットの一つです。後継者の育成や社内での信頼関係構築がしやすく、経営体制の引き継ぎも比較的スムーズに進む傾向があります。
(4)経営理念の浸透、社内の一体感・結束力
経営層が親族で、経営陣と株主の距離も近いため、経営理念や企業理念、価値観の共有が図りやすく、社内の一体感や結束力が強いことも多いです。特に創業家が中心となるケースでは、長年にわたる企業文化の継承が行われやすいのも特徴です。
3. 同族会社のデメリット
一方で、同族会社には独特のリスクや課題も存在します。特に、ガバナンスや透明性の欠如、資金調達の難しさなどが問題となることがあります。
(1)同族・親族間の争い
相続を繰り返し、株主が分散する中で、経営支配株主と経営に直接かかわっていないが株主との間での争いが起きる場合が考えられます。長い歴史や血縁関係が存在する環境では問題はより根深く、複雑になっていきます。
(2)経営の私物化・独善的な運営により、少数株主のための経営が行われない恐れがある
同族会社では、経営権が経営者一族に過度に集中することで、客観性を欠いた独善的な運営に陥るリスクがあります。特に、外部からの牽制や監視が弱い非上場企業の場合、経営の私物化と批判される事態が起こりやすい傾向にあります。
たとえば、会社の利益が主に経営陣の過大な役員報酬や退職慰労金、さらには会社経費の私的流用などに費やされ、少数株主への利益還元がほとんど行われないケースもあります。また、経営者と特別な関係にある人物に対して、能力に見合わないポストを与える一方で、意見の異なる優秀な人材を冷遇・異動させるといった、不当な人事が発生することも少なくありません。
こうした経営は、会社の健全な成長を阻害するだけでなく、少数株主の正当な権利や利益を損なう行為として、法的な紛争に発展するリスクもはらんでいます。上場企業であれば、コーポレートガバナンスの枠組みによって少数株主の利益が一定程度保護されますが、非上場の同族会社ではこうした意識が希薄になりがちです。
そのため、同族会社においても、経営者が自らガバナンスの重要性を認識し、少数株主の存在に配慮した透明性の高い経営を行うことが求められています。
(3)人材登用の幅が狭くなる
経営層が同族関係者に偏ることで、実力ある外部人材の登用やプロ経営者の採用が進みにくい傾向があります。これは、企業の成長ステージや事業の多角化において大きな障害となりうる点です。
(4)少数株主との対立リスク
経営権を持たない少数株主が不満を持ち、株主総会での反対行動や株式買取請求などのトラブルに発展することもあります。情報開示不足や配当方針への不満が原因となるケースが多く、対応を誤ると紛争リスクが高まります。
その他、同族会社には、税務上も特有のルールが設けられており、役員報酬や利益の内部留保については特別な制限がかかる場合があります。
同族会社には経営の安定性やスピード感という利点がある一方で、ガバナンスや少数株主対応などで課題を抱えるケースも少なくありません。
次章では、特に問題になりやすい「少数株主との関係」について、より詳しく解説していきます。
4. 少数株主との関係
同族会社において、経営者一族が多数の議決権を保有している場合でも、少数株主の存在を軽視することはできません。特に、相続や出資などの経緯から意図せず少数株主が誕生しているケースでは、対応を誤ると経営上のリスクとなることがあります。
(1)少数株主の権利
会社法において、株式を一定割合以上保有する株主には様々な権利が与えられています。
- 例えば:
・3%以上の議決権で、株主総会の招集請求が可能
・1%以上の議決権で、帳簿閲覧請求や解散請求権などが認められる場合もある
・少数株主による訴訟提起(株主代表訴訟)の制度も存在
これらの法的権利を行使されることで、経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に内部の不透明な取引や利益相反行為が疑われる場合、少数株主からの追及が経営上の大きな痛手となることもあり得ます。
(2)少数株主との良好な関係構築の重要性
同族会社であっても、少数株主を無視した経営は長期的に見てリスクが高く、経営の安定性を損なう可能性があります。
- そのため、以下のような対応が求められます:
・定期的な情報提供(事業報告や業績の説明など)
・明確な配当方針の提示と履行
・議決権の尊重と株主総会の適正運営
・株主間契約によるルール整備(譲渡制限、買い取り方法の明文化など)
こうした取り組みによって、少数株主の不信感を抑え、トラブルの予防や早期解決が可能になります。結果として、経営の透明性が高まり、外部からの評価も向上することにつながります。
5. まとめ
同族会社は、日本において非常に一般的な企業形態であり、迅速な意思決定や長期的視点に立った経営といったメリットを持っています。一方で、経営権の集中により、経営の私物化やガバナンスの不全といったリスクも内包しています。
とくに、経営に直接関与できない少数株主の立場から見ると、会社の利益が一部の支配株主に偏って分配されていたり、不透明な意思決定がなされていたりすることで、正当な権利や利益が軽視されてしまうと感じるケースも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐためには、同族会社の経営者が、親族内の結束や信頼関係に甘えず、少数株主も含めたすべての株主に対する説明責任や配慮を果たす姿勢が重要です。たとえば、経営の透明性を高める情報開示や、公平な人事・利益分配の仕組みづくりは、少数株主からの信頼を得るための基本となります。
反対に、少数株主の側も、単に「不満を感じる」だけでなく、会社のガバナンスや経営状況を正しく理解し、建設的な対話を通じて関与する意識が求められます。
今後、事業承継や中小企業の経営改善が社会的にますます重要視される中で、同族会社のあり方は、より多面的に評価されていくことになるでしょう。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)