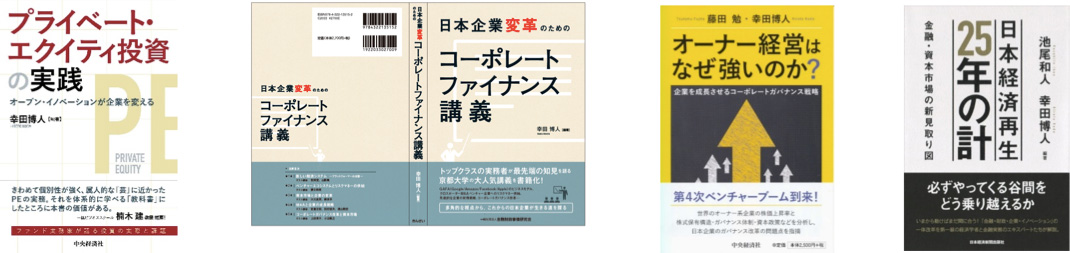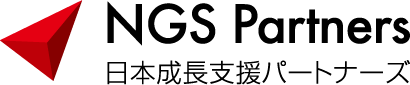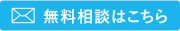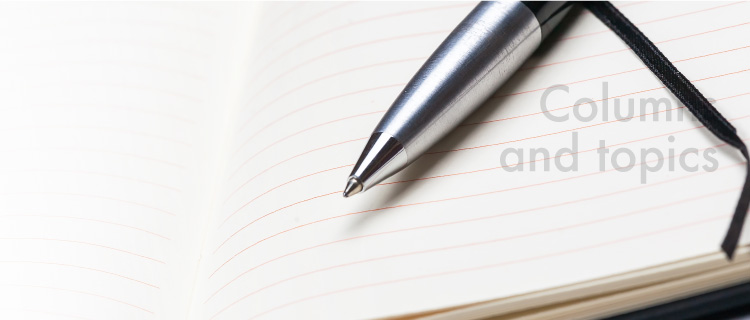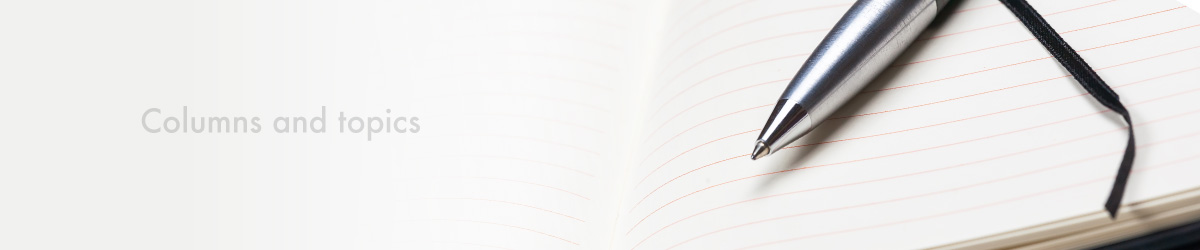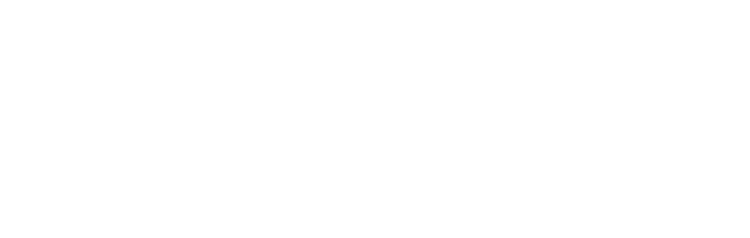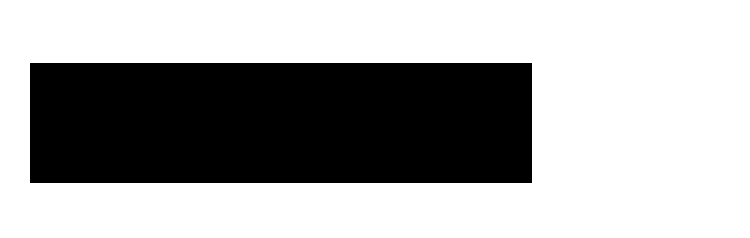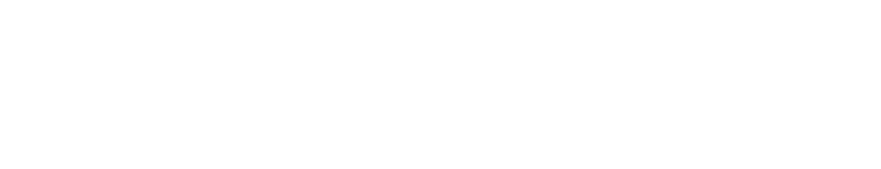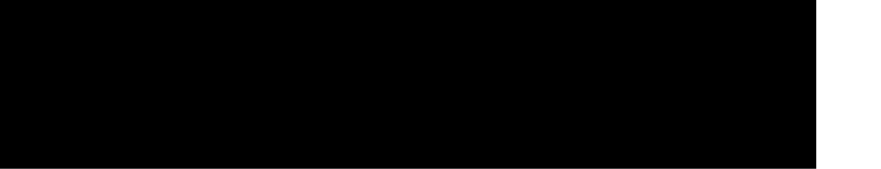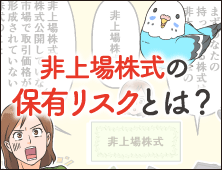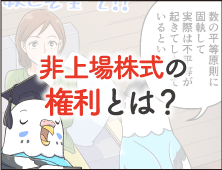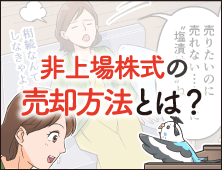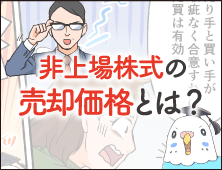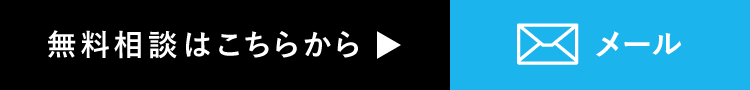親の相続で、思いがけず非上場株式を引き継ぎ、売却を検討している ー そんなご相談をいただくことがあります。
上場株式であれば証券口座に移管され、売却も簡単です。しかし、相続財産に「非上場株式(未上場株式・未公開株式)」が含まれていた場合、話はまったく異なります。市場での売買ができず、株価も分かりにくい。さらに、会社の承認がないと売却すらできない(譲渡制限株式である)。
相続に伴う株式の引き継ぎには、法律・税金・感情のすべてが絡みます。中でも特に注意が必要なのが、相続税の納税資金です。非上場株式の評価額が高額になると、相続税の金額も大きくなります。しかしその一方で、非上場株式はすぐに現金化できる資産ではありません。
今回は、非上場株式を相続した方、あるいは相続が見込まれる方に向けて、「そもそも何が問題になるのか?」「どう備えればよいのか?」という視点から、注意すべきポイントを解説します。
目次
1. 相続財産に「非上場株式」が含まれていたら?
非上場株式とは、証券取引所に上場していない企業の株式のことです。
「非上場株式」は、「未上場株式」や「未公開株式」とも呼ばれます。いずれも意味は同じで、取引市場を通さずに保有されている株式を指します。
上場株式との大きな違いは、その換金性です。 上場株であれば、証券会社のアプリでリアルタイムに価格を確認し、ボタン一つで売却できます。
しかし非上場株式には市場がなく、株価も公的には存在しません。売ろうと思っても、すぐに買い手が見つかるとは限らず、金額交渉や会社の承認など、複雑な手続きを伴います。
さらに、非上場株式は経済的価値だけでなく、「経営への関与」や「親族関係の象徴」といった意味合いも含むため、親族間の感情的な対立や、会社側の警戒感を生むこともあります。
非上場株式が相続財産に含まれていた場合、まず確認しておくべきポイントはいくつかあります。
- ・その株式を発行している会社は、どのような事業を行っているのか
- ・他の株主や経営者との関係性はどうか
- ・株式に譲渡制限があるか(定款に「譲渡には会社の承認が必要」といった記載があるか)
- ・株式の評価額や、それを含めた相続税の総額の見込みはどうか
株式の評価額を把握するには、当然ながら会社の財務状況や業績を確認する必要があります。また、将来の見通しについて経営陣に直接話を聞くことも重要です。加えて、保有している株式が譲渡制限付きかどうかなど、株式の性質についても事前にしっかりと確認しておきましょう。
これらを把握せずに放置すると、後々トラブルや金銭的な負担が大きくなる可能性があります。
2. 相続税は「10か月以内に現金で一括納付」が原則
非上場株式を相続した場合、まず意識すべきは相続税の申告と納税の期限です。
相続税は、原則として「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10か月以内に、申告・納付しなければなりません。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から起算して10か月です。
さらに注意したいのが、相続税は原則「現金で一括納付」しなければならないという点です。つまり、納税額が1,000万円だとすれば、相続発生から10か月以内にその現金を用意し、税務署へ納めなければなりません。
例外的に「延納」や「物納」という制度もあります。延納は一定の要件を満たせば分割払いが認められる制度、物納はやむを得ない事情がある場合に限り、不動産や株式など現物で納税できる制度です。ただし、どちらも事前の申請と審査が必要であり、適用には高いハードルがあります。
相続財産に預金や現金が多く含まれていれば、大きな問題にはなりません。しかし、非上場株式のように現金化が難しい財産が中心の場合、納税資金の確保は深刻な課題となります。
3. 非上場株式は「売りたくてもすぐには売れない」
相続税の納付期限が迫る中で、「持っている株式を売って現金を作ればいい」と考える方も多いでしょう。
しかし、非上場株式、特に譲渡制限のある同族会社の株式は、そう簡単に売却できるものではありません。
第一の壁は「譲渡制限」です。多くの非上場企業では、定款で「株式を譲渡するには会社の承認が必要」と定められています。これにより、会社の承認が得られなければ、たとえ買い手がいても譲渡することはできません。
第二の壁は「買い手が見つからない」ことです。未公開株式には流通市場がなく、価格も不透明。しかも、少数株主であることから経営への影響力は乏しく、配当が出る保証もありません。情報開示が不十分な企業も多く、リスクを取ってまで購入したいと考える買い手は限られています。
仮に買い手が現れても、価格の交渉や、会社との調整に時間がかかります。相続税の納税期限である10か月以内に売却資金を用意するのは、実務的に非常に困難です。
その結果、延納や物納に頼らざるを得なくなったり、資産を売却して現金を捻出する、あるいは相続放棄を検討する ー といった苦しい判断を迫られるケースも少なくありません。
4. 相続対策として今から考えておきたいこと
非上場株式の相続には、法律・税務・感情の複雑な問題が絡みます。
いざ相続が発生してからでは遅く、相続税の納税期限に間に合わない、親族間での話し合いがこじれる、売却の目処が立たない ー といった事態に直面するリスクもあります。
だからこそ、早い段階での「情報整理」と「備え」が重要になります。
まず確認したいのは、会社との関係性です。
株式を保有している企業がどのようなスタンスをとっているか。
- ・株主との関係性
- ・経営者が株式の集中を望んでいるか
- ・譲渡に対して柔軟かどうか
これらは、売却や承継の進めやすさに大きく関わります。
次に重要なのが、株式の評価額の把握です。
非上場株式は、実際には売れない(買い手が見つからないために株価がつかない)株式であっても、税法上は一定の基準に基づいて評価され、その金額に応じた税金が課されます。
さらに、納税資金をどう確保するかも検討が必要です。
たとえば、事前に現金化の可能性を専門家に相談しておいたり、他の資産と合わせて全体の相続設計を見直したりすることで、資金繰りに困らない形を整えることができます。
加えて注意したいのが、親族が経営する同族会社の少数株式を相続するケースか否かです。
自身は経営に関わっていないにもかかわらず、株主としての立場だけが残ることで、対応に悩むことも少なくありません。
親族だから強く買取を求めづらかったり、買取をお願いしても放置される、あるいは「少数株式だから」と軽く扱われ、納得のいかない金額しか提示されないといったこともあります。
適切な対応を取らないと、後々、親族間でのトラブルや資産価値の問題に発展するおそれもあるため、慎重な判断が必要です。
5. いざというとき、どこに相談すればいいのか?
非上場株式の相続に直面したとき、最も大切なのは「ひとりで抱え込まないこと」です。
評価額は高いが現金化できない、親族との関係が微妙、会社とのコミュニケーションが難しい…。このように、法律・税金・人間関係が複雑に絡むのが非上場株式の相続です。
まずは、信頼できる税理士や弁護士と連携し、相続財産の全体像や税務リスクを把握することが第一歩となります。特に税理士には、株式の評価や納税資金の計画についての相談が欠かせません。
一方で、非上場株式の売却支援については、また別の専門性が必要になります。
譲渡制限の有無を確認し、発行会社の意向を整理し、具体的な買い手候補を探し出し、価格交渉や条件調整を行う ー これは、弁護士や税理士だけでは対応しきれない領域です。
実際に、弊社にも相続関係の弁護士から「株式の売却支援をお願いしたい」と、第三者への売却の実務を相談されるケースも増えています。
弁護士は法律のプロではあっても、買い手探しや価格調整といった交渉・マッチングの分野を専門としているわけではないからです。
だからこそ、非上場株式の相続や売却に関しては、それぞれの専門家の強みを活かしながら、連携して対応することが重要です。
「税務は税理士」「手続きは弁護士」「売却支援はそれに特化した実務家」といった形で、課題に応じた適切な窓口に相談することで、結果としてスムーズに問題を整理することができます。
6. 相続をきっかけに、「株式を持つ意味」を見直す
非上場株式の相続は、単なる資産承継ではありません。見えにくいリスクと、想定以上の負担が隠れているケースが少なくないのです。
特に、相続税は10か月以内に現金で納める必要があるにもかかわらず、
非上場株式はすぐには売れず、買い手も限られています。「評価額は高いのに、売れない」「納税資金が足りない」 ー そうしたジレンマに悩む方も多くいらっしゃいます。
さらに、株式には金銭的価値だけでなく、会社との関係性や親族間の感情といった、人間的な要素が強く絡んできます。
業歴が長い会社の株式であれば、なおさらです。そのため、表面的な数字だけで判断するのではなく、一つひとつの状況を丁寧に整理し、冷静に道筋を描くことが求められます。
だからこそ、「相続が起きてから考える」のではなく、起きる前に、誰とどう動くかを考えておくことが何よりも大切です。
税務、法務、売却支援 ー
それぞれの分野に強みを持つ専門家のサポートを得て自分にとって、そして家族にとって最適な選択肢を探っていく。それが、非上場株式の相続における現実的な備え方です。
関連記事
記事協力
幸田博人
1982年一橋大学経済学部卒。日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、みずほ証券総合企画部長等を経て、2009年より執行役員、常務執行役員企画グループ長、国内営業部門長を経て、2016年より代表取締役副社長、2018年6月みずほ証券退任。現在は、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授、株式会社産業革新投資機構社外取締役等を務めている。
主な著書
『プライベート・エクイティ投資の実践』中央経済社(幸田博人 編著)
『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』金融財政事情研究会(幸田博人 編著)
『オーナー経営はなぜ強いのか?』中央経済社(藤田勉/幸田博人 著)
『日本経済再生 25年の計』日本経済新聞出版社(池尾和人/幸田博人 編著)